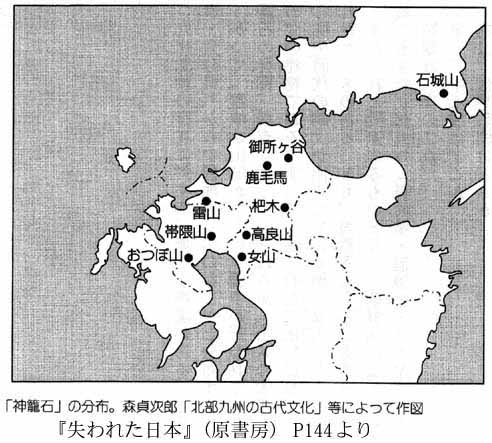
古田武彦
一
それは黄金の三カ月であった。昭和二〇年四月から六月の間である。わたしが村岡典嗣(つねつぐ)先生に親しく接することができたのは、この三カ月だけだった。
しかも、四月は下旬になって授業が開始された。文学部の通例である。六月は上旬まで。これは農村(宮城県志田村 (1) )への勤労動員のため、異例の「授業打切り」であった。八月の敗戦を前にした、閑静なる“ひととき”となったのである。
実質、五〇日間、この間の対面こそわたしにとって至上の日々だった。わたしの生涯の学問研究とは、畢竟すれば、この五〇日間の延長である。その一生の展開にすぎないのである。この一事をわたしは、一瞬も疑ったことがない。
二
先生は学問を語った。本居宣長の学に託して、学問の精神を述べること、常であった。
「本居さんは、ね」これが口ぐせだった。敬愛する身内、たとえば“叔父”のことを語るかのような自然さが、身についていた。わたしの内側に流れこんできた。わたしは東北大学日本思想史科の一年生、入学したばかりの一青年であった。
「本居さんは言ってますよ。『師の説に、ななずみそ』って、ね。お師匠さんの説に拘泥するな、ってんですね。それが本当にお師匠さんを尊敬することだ、っていうこと。これが本当の学問なんですね」
一八歳の頭脳に、先生の一語一語は食い入った。生きつづけた。そして今、この一文を書かしめたまう。 ---- それがわたしの実感である。あれから、六〇年の歳月がすぎた。当時の先生より、わたしははるかに年老いている。
しかしわたしは、先生の足下の一学生としてこの新原稿を呈したいと思う。今それを無上の光栄としているのである。
三
今年(二〇〇四年)五月、一書が公刊された。東洋文庫(平凡社)である。
村岡典嗣著、前田勉編 『新編 日本思想史研究 村岡典嗣論文選』。
収録された論文は、左の一四編、村岡学の形姿をうかがうに好個の諸編である。
日本思想史の研究法について
愚管抄考
国学の学的性格
本居宣長の古伝説信仰の態度
本居宣長の臨終
復古神道に於ける幽冥観の変遷
平田篤胤の神学に於ける耶蘇教の影響
平田篤胤が鈴屋入門の史実とその解釈
徂徠学と宣長学との関係
市井の哲人司馬江漢 -- 思想家としての司馬江漢
妙貞問答の吉利支丹文献 として有うする意義
日本倫理思想史上西洋思想との交渉
日本学者としての故チャンブレン教授
日本精神を論ず -- 敗戦の原因
以上である。
他にも無論、好篇は存在する。たとえば、
「明治維新の教化統制と平田神道 -- 信教の自由の公認まで」
(『続日本思想史研究』岩波書店)
がある。明治初期の、平田神道の一派によって行われた「教化統制」が、(いわゆる「信教の自由」 ---- 明治憲法の成立後も)なお今日までその思想的影響をとどめている状況。それを深く考えさせる名篇である。紙幅の関係上、やむをえず、割愛されたものであろう。
本書末尾におかれた、編者による「解説」は力作である。村岡学の全体像とその特徴が各面にわたって論ぜられている。傾聴すべきところが多い。
さらにすすんで、村岡(以下「先生」を除かせていただく)の場合、各個の論文が啓発的なのに対し、「通史」的叙述の場合は「ひどく単調なものとなっている」と指摘する。そしてその「平板さ、単調さ」の一因として、村岡が「新カント派の歴史哲学にもとづいている」ことをあげている。興味深い指摘だ。
村岡の著作のうち、もっとも広く普及したという『日本文化史概説』(岩波書店、昭和一三年)がその例にあげられているが、他にも「日本精神論」にかかわる通史的叙述もまた、その類例となるかもしれない。
しかしながら、これは果たしてドイツ西南学派と呼ばれるヴィンデルバントなどの「新カント派」の、村岡に与えた影響の責任に帰せられるべきものであろうか。
編者は、村岡の通史的叙述を、同時代の羽仁五郎の論考(『日本における近代思想の前提」所収)と比較している。それによって「この思いは募る」と書いている。
社会科学、さらにはマルキシズムを背景とした羽仁の筆致は、歯切れがいい。「平板」も、「単調」もない。それは確かだ。
しかし、真の問題は果たして、そこにあるのだろうか。その羽仁がかりに「日本思想」の通史を書いたとして、果たしてそれは現在“読むに耐える”ものであろうか。わたしには、深い「?」が湧きおこるのをとどめえないのである。
編者ももちろん、この「新カント派、原因説」をもって、“すべて”としているわけではないであろう。それを「一因」としているのであるから。
わたしには、羽仁はもちろん、村岡に対しても、“魅力的な通史”を書かせない根本原因、それは実は、他にあるように思われる。
本論文は、その回答を、少なくともその回答の方向を、さししめすこととなるであろう。
四
村岡学に内蔵せられている諸問題点、それを以下率直に述べさせていただくこととしたい。
第一は、「同時代史料」問題である。三世紀の三国志、五世紀の宋書、七世紀の隋書といった同時代史書の中に報告せられた「倭国情報」ないし「日本情報」について、村岡は一切分析したり、考察することがなかっだ。
倭人伝中で有名な「鬼道に事え、能く衆を惑わす」という、卑弥呼に関する情報が、貴重な「日本思想、情報」であること、疑いがない。
また注目すべき「持衰じさい」記事も、当然ながら「日本思想の成立」と深い関連をもっていよう。
さらに「始め死するや停喪十余日、〈中略〉他人就いて歌舞飲酒す」の一節も、「日本思想」を論ずるさい、到底看過しえぬところであろう。
このように貴重な「倭人伝情報」に対し、これを「認識せられたものの再認識」というフィロロギー(アウグスト・ベェク)の立場から、周到なる分析と論及が村岡によってなされていたら、と惜しまれる。陸離たる光彩をしめしたことであろう。しかし、それはない。
五
第二は、右につづき、隋書イ妥国伝との対比である。ここに有名な「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙なきや。云々」の一節のあること、知らぬ人とてない。
その天子の名は「多利思北孤」であり、太子は「利歌弥多弗利」とされている。その上、その風土として、
「阿蘇山あり。その石、故なくして火起り天に接する者、俗以て異となし、因って[示壽]祭を行う〈下略〉」
イ妥国のイ妥(たい)は、人偏に妥。ユニコード番号4FCO。
[示壽]は、示編に壽。JIS第3水準ユニコード79B1
という、瞠目すべき一文が存在する。しかし、これに対して村岡の分析し、論述したものをみない。
わたしの、村岡に接した三カ月において「十七条の憲法」に関する特殊講義があった。日本書紀中の当該個所の印刷された資料が渡された。一字一句の解説だった。学生は(岩井源一郎君と共に)二人だけであった。
農村への勤労動員のため、その講義は「完結」することなしに終わった。わたし自身も、何の知るところとてなき一学生にすぎなかったから、日本書紀の伝える「推古天皇と聖徳太子」の存在と、右のイ妥国伝の内実との間に横たわる、重大な「ラグ(ずれ)」について、これを“問う”こともなかった。
今、村岡の全著作にふれてみても、この「ラグ」に取り組み、苦渋したあとをみない。「平板」とされ、「単調」となるのも、あるいはやむをえぬところだったのかもしれぬ。
六
第三は、同じく、倭入伝と古事記・日本書紀との間に横たわる、「根本のラグ」である。
倭人伝に明記されたところ、それは「卑弥呼と壱与」という二人の女王の存在である。
これに反し、古事記の天皇名、その歴代のしめすところ、右のような「女王たち」の存在はまったくな。論者の中には「ヤマトトトモモソヒメ」などの女性をこれに“当て”ようとする者があるけれど、それらは畢竟“苦しい弁明”にすぎぬ。なぜなら、一方の「女王」は中国の天子から「親魏倭王」の称号を与えられた「倭国の中心の王者」であるから、「歴代の天皇名」中に名を列しえぬような存在とは、おのずから選を異にする。大義名分上の位置をまったく異にしているのである。
他の論者の中には、倭人伝中の「女王たち」をもって、大和の王者にあらず、九州の一土豪の女酋長とみなす者がある。
けれども、これもまた「史料事実」に反する。一方の卑弥呼は、中国の天子から「倭国の中心の王者」と認知された存在である。これに対し、古事記の「歴代の天皇群」には、そのような国際的な認知はない。中国や東南アジア諸国の認知するところではまったくないのである。
とすれば、「一地方の土豪の首長」と目さるべきは、いずれであるか。先入観をもたぬかぎり、自明ではあるまいか。
このような「ラグ」について、村岡には、残念ながら“心を悩ました”痕跡を見出すことができない。
七
第四は、倭人伝と日本書紀との対比である。周知のように、書紀には長巻「神功紀」がある。その中に「倭の女王」(三九年)、「倭国」(四〇年)、「倭王」(四三年)といった形で「魏志」が引用されている。今問題の卑弥呼に関する文面である。
次に、「六六年」に至って「倭の女王」の貢献記事が掲載せられている。
当然、これらの「倭王」ないし「倭の女王」とは、他にあらず、神功皇后その人である、との筆致、否、「史書としての構成」をとっている。
思うに、古事記と日本書紀との間の「ラグ」を論ずるとき、この「神功紀の有無」以上の二大ラグ」は他にない、ともいえよう。なぜなら、文面の一隅や一解釈にあらず、「天皇の列名」という、史書の根幹をなすべき編成上の“新立”だからである。
この“新立”の根本の動機は、右の四個の引文によって明らかである。
「古事記の天皇列名には、卑弥呼たちに当たる存在がない」
この一事だ。前項にわたしの率直に指摘したところ。それはまさに日本書紀の編者の“深く悩んだ”ところ、そのものだったのである。その結果、
「古事記が捨てられ、日本書紀が新たに創られた」
といっても、おそらく本質的には、過言ではないであろう。卑弥呼と壱与に相当する女王なき古事記の「形」では、三国志等の永い史書伝統をもつ、中国および東アジア世界の認知をうけえない。八世紀の近畿天皇家はそのことを十分に察知したからである。
わたしたちは今、古事記と日本書紀を“併せ読む”という幸せを有している。南北朝の一四世紀に至って、真福寺本古事記が「偶然の手」によって“登場”させられたためである。それまでは永く「日本書紀の単一世界」がつづいていた。たとえば、紫式部や親鸞や日蓮たちは不幸にも「古事記を知らなかった」世代に属している。
しかし、日本書紀の編者たちの意図では、それでよかった。そうあらねばならなかった。それゆえにこそ、続日本紀の元明天皇和銅五年の「古事記撰進」記事のあるべきところに、それがない。あえて「カット」されたのである。
もちろん、記・紀の間の「相違」問題は、多々ありえよう。各論者の各論尽きぬところである。しかしながら、その根本要因が右の一点、すなわち「神功紀の新立」にあったこと、これを疑うことはおよそ困難なのではあるまいか。
なおこの点につき、二つの問題点に注意しておこう。
その一は、「魏志の引用」後時付加説は成立不可能でること。この点、すでに田中卓氏の詳論せられた通りである。(2) たとえば、もし本来、右の四個の「引文」がなかったとすれば、それらの条項の多くは、その「引文」のみで成り立っているのであるから、史書としての記載形式を“失う”のである。
その二は、日本書紀全体の「時間軸の立て方」が、この神功紀を原点としていること。この神功紀の「時間帯」を、卑弥呼のいた三世紀におき、そこから“さかのぼり”、そこから“降らせて”いる。この点、今は、学界周知のところである。
八
第五は、右の問題にとっての核心部分である。それは「二人の女王、同一人」問題である。
先の三九年・四〇年・四三年の三項が、倭人伝の卑弥呼に関する記事であることは疑いがない。倭人伝そのものと対比すれば、自明である。
これに反し、六六年項は、卑弥呼の記事ではない。
「是年、晋の武帝の泰初の二年なり。晋の起居の注に云はく、武帝の泰初の二年の一〇月に、倭の女王、譯を重ねて貢獻せしむといふ」 (3)
倭人伝によれば、魏の正始八年(二四七)項につづき、有名な「卑弥呼以て死す」の記事が現われている。混乱のあと、卑弥呼の宗女壱与が立ち、中国へ献使する。「白珠五千孔」などの壮麗なる貢献記事をもって結ぶ。
これは「魏」にあらず「西晋」に対する貢献である。三国志の魏志を作ったのは、西晋朝であった。それゆえ、“魏から西晋へ”の、いわゆる「禅譲の正当性」を立証すること、それが魏志の末尾におかれた「倭王による西晋貢献」記事のもつ、大義名分上の意義であった。
以上によってみれば、この「西晋貢献」が卑弥呼の遣使にあらず、壱与の遣使であったこと、明白である。
ところが、日本書紀は「卑弥呼の遣使、三回」と「壱与の遣使、一回」を併せ、その四回とも「神功皇后の遣使」として“扱って”いる。これを、中国と東アジア世界に対して「周知」させようとしているのである。
もちろん、中国や東アジア諸国では、四回の遣使が、「甲」(卑弥呼)、「乙」(壱与)二人の女王による遣使であることを“知って”いる。
これに対して、日本書紀は「当事国」として、「あれは実は、一人の女王である神功皇后の遣使だったのです」と、“改正“し、“正しい史実”を伝えようとする。これがこの史書編成にとって、重要な一眼目点だったのであった。
いかに、中国や東アジア諸国といえども、このような「当事国からの申し立て」に対して、一笑に付することは困難であろう。
このような一方の「企図」をくつがえすもの、それが他でもない、古事記の存在である。そこには「神功記」など存在しない。それどころか、七世紀の推古天皇代に至るまで、「女王在位」の痕跡すら、存在していなかったのである。古事記ももちろん、「当事国」の史書だ。しかも、一私史などではない。天武天皇の「認承」をうけ、元明天皇による「撰進の命」をうけて作製された「正史」である。しかしそこには、「神功記」がない。
日本書紀の編者たちは、否、元正天皇当時の実力者たちは、八年前の「古事記」を廃棄した。さらに“各年月日、逐次記録”の形の史書である続日本紀(の元記録)から、その撰進記事(元明天皇代)そのものまでカットさせねばならなかった。その“家庭の事情”ならぬ「王朝内の事情」が手にとるようにうかがわれよう。 ---- あの応安五年(一三七二)、真福寺本古事記の出現が、その「夢」を破ったのである。それが失われた古事記「復活」のもつ意義。激震だった。
古事記尊崇を人生の道標とした本居宣長には、このような「成立」問題に関する視点はなかった。自国の古事記を尊崇し、異国の書への傾倒を排除する、有名な、彼の「イデオロギー」が、あるいは聡明なる眼識をくもらせたのではあるまいか。
残念ながら、村岡学においても、このような問題に対する分析と再認識の手はついにおよぼされていない。
九
第六、今や学界周知ともいうべき、右のテーマをここであらためてとりあげたのは、他でもない。
村岡が「日本思想」中の最大の特色として、くりかえし宣明してやまなかった「あかき心」との関係である。
すでに大正九年の論稿において、
「邪心はきたなき心で害意、清明心は『かくさはぬあかき心』できたなからぬ心である」
(「古神道に於ける道徳意識とその発達」『日本思想史研究』)
と述べ、昭和二〇年九月、敗戦後の講義においても、
「国民思想の遺産としての古語の価値は、最も尊重されねばならぬ。而してかくの如きものとして、吾人の最も適当に挙示しうるのは、すでに相応に普及するを見た、あかき心、きよき心等の観念である」(「日本思想を論ず」東洋文庫本、所収)
といい、二六年前と同じ、記・紀における天照大神と素戔鳴尊との誓約の一段があげられている。「清き心」「あかき心」の証例である。
村岡の生涯を貫く、「日本思想」に関する、史料上不可欠の実例がここにみられる。そのようにみなしても不当ではないであろう。
では、間おう。
右に挙げた「二女王=神功皇后」というような編成は、果たして「清き心」「あかき心」にもとづく編成、といいうるものであろうか。
日本書紀の編者がみずからその、「非史実」であることを自覚していたこと、それは「卑弥呼」「壱与」という、各個の実名を避け、代わって四条とも、「倭の女王」「倭国」「倭王」といった一般称号を“主”としていること、この基礎事実からも疑いえない。これを偶然の筆法とはみなしえないのである。
その上、何よりも、日本書紀の編者は「古事記を読んでいた」のである。わたしにはこの一点を疑うことができない。とすれば、日本古来の「天皇の列名」中、卑弥呼・壱与に当たる存在なきことを、誰よりもよく承知していたのである。承知していたからこそ、あえて天武・元明の両天皇“お声がかり”という尊貴なる古事記自体を、廃棄せしめた。さらにすすんで続日本紀に掲載されるはずだった「和銅五年正月廿八日」頃の撰進記事を断固「カット」せしめたのである。日本書紀の天武紀においても、「(古事記)稗田阿礼、誦習」の影さえない。
これが「清き心」あるいは「あかき心」のなすべき所為なのであろうか。
一〇
第七、もちろん、これに対する「反論」は、容易に幾多予想しうる。たとえば、「理想と現実とはちがう。村岡の挙揚したのは、その中の理想である」とか、「日本書紀の神功紀の正しさを(当時においては)、編者は誠心誠意、信じて疑わなかったのである」とか、「道徳思想の問題を、史書編成というような、高度の政治判断に立つべきテーマと直結させて論ずるのは、不当である」等々。他にも、幾多の各種の立論があろう。それはよい。
しかし、今問題とすべきは次の一点だ。村岡の依拠した史料が古事記・日本書紀等である以上、その史書成立の「原点」に携わる問題において、その両書が“挙揚”する徳目と、あるいは相反すべきテーマがここに見出されたとき、それを一切「等閑視」するとすれば、それは果たして後代の歴史学研究者として誠実の道であろうか。
わたしたちが、いわゆる「日本的精神風土」のために、そのような問題にあえて立ち入らず、それをもって「つつしみ」とし、「常識」としていたとしても、世界の、これからの学者はそのような「暗黙のルール」に従いつづけようとは、決してしないであろう。識者が言うように、「日本の常識は、外国の非常識」なのであるから。
少なくとも、村岡がこの一点に深く探究の目を向け、「認識せられたものの再認識」への道を、着実に前進しようとしていたならば、後代の鋭い論者から「平板」や「単調」の評をうけることは決してなかった。わたしにはそのように思われるのである。
一一
次は、「考古学的出土物との対比」問題である。(形式上、“通し番号”とする)
第八、村岡学においては、考古学的出土物との関連やその対比にふれることがない。
この点、わたしはかって直接、お聞きしたことがある。その答えは、
「わたしの学問は、フィロロギーの中で、文献だけを扱っています」
と。すなわち、アウグスト・ベェクのフィロロギーの研究対象は、決して「文献」だけではない。たとえば、ギリシャを対象とする場合、ギリシャで生み出されたソクラテス、プラトンなどの文献だけではなく、ギリシャの建築や演劇や伝承や体操や競技、あのオリンピアで競われた戦車等の競争も、その研究対象であった。いずれも、「人間の所産」である以上、当然「認識せられたもの」に属する。従ってその「再認識」こそが、フィロロギーの目途するところ、その本番をなしたからである。
この点、この「フィロロギー」の語を、「文献学」と記す者があるのは、(「目くじら」立てる必要はないかもしれないけれど)実際は、正しくはないのである 。
この点、村岡の方法意識は鮮明であった。“本来のフィロロギーそのものは、文献だけではないが、わたしの「研究範囲」は、文献だけにとどめる”との立場である。
それはそれとして、“とがむべき”ものではないであろう。まだ、明治以降、このフィロロギーの「日本への(初歩的)移植」ともいうべき時代、これに“多く”を望みすぎるのは、むしろ酷というべきであろうからである。 ---- 「自己抑制」である。
それはそれとしても、実際に「古代」を研究し、「古代の日本思想」を明らかにしようとした場合、この「自己抑制」は果たして“学問的に”妥当か。また“成立しうる”のか、否か。との「問い」が実は必然的とならざるをえないのである。なぜか。
たとえば、銅鐸。日本列島中、すでに三〇〇個以上の出土をみている。あの銅鐸が、古代、弥生時代における「人間の製作物」であること、疑いを入れない。しかもその形状や内実、その文様やデザインの類をふくめて、古代人の「古代の思想表現」の一をなしていることもまた、疑う人はいないであろう。
しかるに、古事記、日本書紀や風土記等の「文献」に、一切その存在をみせない。稀にその“出土”を記すものがあっても、それの担うべき「古代思想」の叙述など、一切存在しないのである。
従って、もし「日本思想」を叙述しようとする場合、「文献」のみを依拠資料とすれば、必然的にこの「銅鐸」という存在を“排除”することとならざるをえない。それをとりまく「祭祀」、それをささえる「古代信仰」などはまことに瞠目すべき研究対象である。すでに三〇〇個以上の出土をみている。ということは、実際に存在したものはその五倍・一〇倍以上。すなわち日本列島の中枢部、中国地方、近畿地方、東海地方にまたがる、一大古代文明、すなわち「一大古代思想圏」の存在を明らかにしめしている。これらをすべて「カット」しておいて、果たして「日本思想」の歴史と“自称”しうるのであろうか。 ---- 否。
しかも、この「銅鐸」問題には、もう一つの重要な側面がある。「三種の神器」問題である。
古事記、日本書紀においてこの「三種の神器」問題が重要なテーマをなしていること、著名である。先の天照大神の「天孫降臨」をめぐり、この「三種の神器」(正確には「三種の宝物」)問題がくりかえし、語られ、叙述されていること、一目瞭然たるものがある。
ところが、それと“同時期の存在”すなわち「弥生の宝物」であり、「一種の神器」と呼ぶべき、この銅鐸については、記・紀ともに一切これにふれない。不可解である。
けれども、逆に、この「不記載」にこそ、意味がある。絶大の意義があるのだ。
なぜなら、記・紀が「三種の神器」のことを、くどいほ、どくりかえして書いているのは、ただ「そこに、それがあったから」ではない。
自家の王朝の「権威」を“証明”するために、その記載が「必要」であり、「不可欠」であったから、書いているのである。そのように理解するのが、正当だ。
だとすれば、あれほど“目立つ”宝器、いわゆる「一種の宝器」について、一切記述がないのは、「その存在に気づかなかった」からではない。逆だ。
「銅鐸は、他者(他の王朝)の宝器であるから、書かない」のである。これ以外の理解はありえない。
史家とは、何者であろうか。勝者の御用史家なのであろうか。一定の王朝の「主張」するところのみを挙揚し、「主張しない」ものは、打ち捨ててかえりみない。それが歴史学の任務なのであろうか。
本居宣長は、よい。彼は古事記、そして日本書紀を尊崇した。尊崇し抜いた。「からごころ」「ほとけごころ」を排除した。そしてみずからは「やまとごころ」にとらわれたのである。それを、よしとした。しかし、その「やまと」の大地からは、見事な中期銅鐸、鍵・唐古の銅鐸製造遺跡が出土しつづけている。しかし宣長は、そのような「やまと」に対しては、一切、目も耳も傾けなかったのである。
けれども、近代の歴史学の一つとしての日本思想史学の研究者が、そのような「信仰」と「イデオロギー」に、その「わく」の中にとどまりつづけることが果たして許されるのであろうか。
わたしには、日本思想史学にとって、今後、前進すべき道はおのずから明らかであると思われるのである。
一二
第九、右の分析は次のテーマをしめした。「文献には、書かれていることと共に、書かれていないことが重要である」
この金言を赤裸々に立証するもの、それは「金印」問題である。
後漢書の倭伝には、次の文面がある。
「建武中元二年(五七)、倭奴国、奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す (4) 」
右の国名を「倭の奴な国」と読む(たとえば、岩波文庫)のは、不当である。金印の読みを「漢の委わの奴な国」と読む、三宅米吉の「三段読法」に“合わせる”ための読法である。米吉は「委わ」(=やまと)を日本列島の中心国とみなし、「奴な」(那の津。博多)を、その従属国とみなしたのである。「ヤマト中心読法」だ。しかし、中国の印制には「AのBのC」という「三段読法」はない。ことに「金印授与」は、当該部族の「中心の王者」であることを認知するための政治行為であるから、なかんずく、ありえない。「三段読法」は、印制上、無法である。「漢の委奴ゐど国王」と読む。後漢の光武帝の宿敵「匈奴」(たけだけしい部族)に対して「委奴」は“従順な部族”の意である。
それはともあれ、日本列島の「中心の王者」の認定であること、疑いがない。
これに反し、古事記、日本書紀ともに、この「金印授与」ないし「金印受領」の記事がない。まったく存在しないのである。すなわち、同じ「文献」でも、(甲)中国側の文献と(乙)日本側の文献(記・紀)と、両者まったく「認識を異にしている」のである。 ---- では、いずれが是か。
この回答は。天明四年(一七八四)の志賀島からの金印の出土によって、決定された。(甲)が正しかった。(乙)は非。中国側の「文献」の記述が正しく、日本側の「文献」の記述(書いていないこと)がまちがっていたのである。
けれども、先の「銅鐸」問題の検証がしめしたごとく、記・紀はただ、この「重大事件」に気づかなかったから、書かなかった、のではない。そんなことはない。これほどの重大事件に対して、そのような「不注意ミス」など、考えられないのである。では、なぜか。
「後漢の光武帝当時(紀元後、一世紀)、近畿天皇家は、中心の王者ではなかった」
それゆえに、気づいていながら、あえて「書かなかった」のである。先述のように、三国志の魏志の存在に気づき、あれほどの「苦心と新案」の編成に向かった日本書紀の編者が、後漢書の存在に気づかないとは。そんなことは考えられないのである。その後漢書をみれば、倭伝に目をやらぬはずはない。目をやれば、そこに出色の、右の一節に「目をこらさぬ」はずはない、まったくありえないのである。
それゆえ、やはり「知りつつ、あえて書かなかった」 ---- このように帰結する他はないのである。なぜか。
先にのべた通り、この一世紀当時、いまだ己れ(近畿天皇家の代表者)は、決して「中心の王者」ではなかった。この自己告白である。
以上の問題は、
(A)自国の文献(記・紀)と他国の(自国に関する)文献とを対比する。
(B)日本列島内の「考古学的出土物」を、無視、あるいは軽視せず、これと対比する。
この立場を守る限り、誰人にも至らざるをえぬ帰結である。しかも、この場合、問題の「志賀島の金印」は、弥生時代における「三種の神器の中心分布地帯」の中枢から出土している。博多湾岸だ。この一点が重要である。
すなわち、「三種の神器」圏の中でも、近畿天皇家は本来、「主流」ではなく、「傍流」にとどまっていたのである。
記・紀の「神代の巻」を飾る、否、そこにあふれている「三種の神器」記事のもつ歴史的意義を理解する上で、このような根本認識は果たして不要だろうか。否、まさに不可欠である。
あたかも、科学実験のさいの、あのリトマス試験紙のように、この金印の出土は「赤」と「青」を簡明に峻別すべき決定的な力を宿していたのである。
けれども村岡学においては、残念ながら、歴史学の眼晴ともいうべき、このリトマス試験紙が一切使用されていなかっだようである。
一三
第一〇、右の「金印」問題は、いわば頂門(ちょうもん)の「一点」である。しかしながら、より重要なもの、それは「神籠石」の存在である。これは広い分布圏をもつ。いわば「一帯」の問題であった。(図1)
この「神籠石の分布領域」の中心は、明らかに“太宰府と筑後川領域”である。まかりまちがっても、「大和」ではない。奈良県や大阪府を“取り巻いて”はいないのである。これが「地域」だ。
では、この成立の「時間帯」はいかに。“六〜七世紀”とされているが、近年の放射性炭素測定(14C)や年輪年代測定法によれば、従来の「考古学編年」が、“一〇〇年前後”さかのぼる可能性が高いことから考えると、“四〜五世紀”にまで、その「上限」がさかのぼる可能性が少なくない。 (5)
この神籠石は、かって「神域か山城か」という論争対象となっていたが、佐賀県のおつぼ山神籠石などの発掘調査によって、礎石、立柵跡などが確認され、「山城」であったことが判明した。
右の経過そのものがしめしている。この巨大な、山上(中腹)構築の城塞が、古事記や日本書紀にその永年の築城経過が一切記されていないこと自体、この築造主が「大和朝廷」あるいは「近畿天皇家」ではなかったこと、この事実を“偽りえず”告知しているのである。
しかるに、現代の歴史学者も、考古学者も、そのほとんどすべてがこの「巨大山城群」をもって、「大和朝廷」や「近畿天皇家」による築造であるかに“移し”ている。
そのためには、いずれも「事実に対する冷静な観察者」にあらず、「口の技術」に頼る、多弁の弁明者におちいっている。そうならざるをえないのである。
しかし、たとえ「日本国内の人々」に対して、そのように“言いふくめ”えたとしても、理性と常識ある外国の研究者や一般の人士が、このような「非道理」を容認する日は決して来ないであろう、永久に。これ、村岡学の対面すべくして対面してこなかったテーマであった。
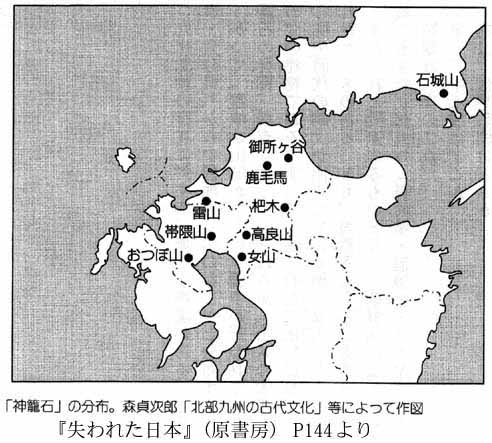
一四
第一一、村岡学にとって、なぜこの「神籠石群」の存在が問題となるか。これを考えてみよう。もっとも端的な事例、それは先の「憲法十七条」の問題に現われている。その有名な第三条には、次のようにある。
「詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す〈下略〉」
右によれば、「推古天皇----聖徳太子」の王朝は、倭国の「中心王朝」であること、およそ疑いがない。(A)
ところが逆に、「神籠石山城群」が取り囲む“中心領域”は、「大和」や「飛鳥」ではない。----筑紫である。(B)
この(A)と(B)との間の矛盾、これはいかに解くべきであろうか。
これに対する「回答」は、明快である。
〈その一〉(B)のしめす「位置関係」は、動かしようはない。
〈その二〉先にしめした「神功紀の新作」問題のしめすように、日本書紀は決して「正直な史書」ではない。「清き心」「あかき心」を説きながら、みずからの「史書製作」の姿勢は、決して誠実、誠意とは、いいがたいのである。
〈その三〉右の対比するところ、その率直な帰結は、意外ながら次のようである。
「『憲法十七条』が創られた場所、それは“大和”ではない。“筑紫”である」
と。
論理のさししめすところ、右の帰結を避けることはできない。これを今、村岡の霊前につつしんで報告したいと思う。
一五
第一二、右の帰結に対する“裏付け”について述べよう。
〈その一〉太宰府の都府楼あとには、次のような地名が残されている。
朱雀門(天子の宮門)----前面
紫震殿(天子の宮殿)----中心の奥、右手
大裏(だいり、内裏)----中心の奥手
大裏岡(だいりおか)----右の背後の岡
このような「天子の宮殿」特有の地名が遺されていることと、偶然ではない。ただ“いっときの天皇の仮の宮”に対して名付けるべき、また“名付けうる”地名ではないのである。
〈その二〉隋書イ妥国伝中の太子の名として
「利歌弥多弗利」
という“名称”があり、各論家、各注解者ともこれに悩んできた。
しかし、この一句は次のように読むべきものと思われる。
「(太子を名づけて)利と為す。歌弥多弗の利なり」
である。「歌弥多弗」は“かみたふ”であり、「上塔」をさす。現在、九州大学の地(旧地)は「上塔の本」「下塔の本」という字地名をもつ。仏教の塔寺の跡地であろう。
この太子は、この地の塔寺にいた。そして仏教の「利生化他」の意の「利」という一字名称を「名」としていたのである。倭の五王の「讃・珍・済・興・武」といった一字名称に習ったものであろう。この「済」もまた、「衆生済度」の意の一字名称であろう。
父親の「多利思北孤」(“足りし矛”)は、倭風名称であり、その国書の中の自署名に書かれていた正式名称と思われる。
その国書に「副署」したのが、太子であり、そこには「上塔の利」と自署されていた。中国側は、それをそのまま表記したのである。従来の論者は、この両名(天子と太子)をもって、「大和の王者と太子」と“きめつけて”いたため、種々の“工夫の弁舌”を必要としていたのであった。
〈その三〉隋書イ妥国伝について。このイ妥は、倭国がその国書において、自国名を、
「大倭たいゐ」
と記していたのに対し、これをおとしめ、「よわい」という意味の、
「イ妥たい」
へと“変え用いた”のであろう。
かって三国志において述べられていたように、新の王莽が「高句麗」に対し、
「下句麗」
の「変名」を当てたことと、相類似する、姑息な「手法」である。
有名な「日出ずる処の天子、云々」の一句は、現代(明治以降)の日本の教科書では、「(聖徳太子が)自国を誇った名文句」のごとく扱われてきたけれども、その実、隋書を制作した唐朝の立場では、“夷狄にして「天子」を称した無礼者”あるいは“中国にあらずして「偽天子」を称する偽輩”という「扱い」に他ならなかった。「許しえぬ倭国の非」の証拠としての表現である。
さらに「大倭」の「大国」称号に対して、これを“変型”せしめ、「弱い」意味の一字をもって、その「国号」に変えたのであった。
以上、いずれも「日本思想」を論じて看過しえぬところ、「憲法十七条」を釈して不可避のところであること、いうを待たない。
けれども、考古学的出土物を扱わず、神籠石巨大城塞群の存在を「認識せられたもの」とみなすことのなかった村岡学にとって、このように興味深き史上の問題に対しては、ついに「再認識」の刃を向けることがなかったのである。
一六
第一三は、「記・紀記述と考古学的分布との対応」問題である。
記・紀の神代巻における中心テーマが「天孫降臨」であること、一目瞭然としている。けれども、その到着点としての「降臨地」の所在に関しては大きな疑問点が存在する。
「竺紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降ります」
(古事記)
本居宣長は右の「竺紫ちくし」をもって“全九州”とみなし、「日向」を“ひゆうが”(宮崎県)とし、「高千穂」を“高千穂峯”もしくは“霧島峯”とした。そして肝心の「くじふるだけ」に対しては、「山名失われたため、不明」として、これを見過ごしたのであった。(古事記伝)
以後、この「天孫降臨」を論ずるさい、古典学者、歴史学者、考古学者、哲学者、評論家等のいかんを問わず、この「宣長流」に従って、これを怪しむ者をほとんどみないのである。
わたしはこれを「非」とした。その理由は要記すれば、左のようである。
第一、「竺紫(ちくし)」は今の福岡県であって、全九州の呼び名ではない。筑紫(現地音、ちくし)も同じ。
第二、福岡県の中の「日向」は“ひなた”と読み、福岡県の西隅付近に当たる字地名である。(日向山、日向川、日向峠あり)
第三、右の日向山日向峠をふくむ高祖(たかす)山連峯中には、「クシフルダケ」が実在する。
すなわち、古事記において「天孫降臨地」とされているのは、南九州ではない。北部九州の中の、糸島・博多湾岸に臨む、高祖山連峯である。(古田『盗まれた神話』)
今「宣長学の方法論」に目を向け、これを再点検してみよう。
宣長は記・紀を尊崇した。彼は時として、「古事記、一辺倒」のようにいわれているけれど、然らず。古事記と並んで書紀をも尊重した。そのため、おのずから、時として、
「書紀の立場から、古事記を読む」
結果となっていたのである。たとえば、書紀には、
「長じて日向国の吾田邑の吾平津媛を娶り、妃と為す」
(神武紀)
とある。「日向国」とある以上、これは「ひなた」ではない。「ひむか(ひゅうが)」である。宮崎県だ。
だから、宣長は、神代巻その他の「日向」をもってすべて「ひむか」(宮崎県)と信じたのである。それは、記・紀のいかんを問わなかった。そのため、「筑紫とは全九州」というような“誇大説”へと奔ったのである。
(宣長がその“証拠”とした「筑紫島」〈神代記「国生み」〉の表記は、「伊予之二名島」「隠伎之三子島」などと同じく、全島中の一画に己が視点をおき、その「部分地名」を基点として全島名に“代えた”ものである。海洋民側の命名であろう。従って宣長がこの一例をもって展的に「全九州が筑紫と呼ばれた」証拠と考えたのは、まったく非である。)
さらに、肝心の一点がある。古事記の神代巻(および神武記)には、「日向国」の表記存在しないことである。このような表記は、後代(仁徳記等)のことだ。
だから、古事記の中の「天孫降臨」の一節の「日向」をもって「日向国」と読むのは、あやまっている。古事記を単一の、独立した古典とみなさず、日本書紀に“従属”させて読んだ。それがこの「宣長の訓法」のもつ意味だったのである。
なぜ、このような事態が生じたか。それは宣長が「日本書紀、新立」の経緯に意を払わなかったからである。いいかえれば、「古事記を廃棄した」その人々が日本書紀を創った。この明白な、ことの因果関係に“目をつむり”、この肝要事を等閑視したからである。この一点に注視すれば、「記・紀を並び尊崇する」とか、「紀に従って記を読む」などという手法を、採用できるはずはなかったであろう。しかし「ふるごとを尊重する」という美辞におおわれて、宣長はこの肝心の視点を失っていた。その点、村岡学もまた、遺憾ながら別軌に出ずることがなかったのである。
これに対して「反論」があるかもしれぬ。「村岡の目指したものは、神話中に表現された日本思想そのものである。従って記・紀の成立事情の相違などとは関係がない。」「またそれもとづくという、天孫降臨の現在地なども、村岡の関心の向かうところではなかった」などと。
では、問おう。村岡の著名の論文に「愚管抄考」がある。昭和二年の脱稿、『日本思想史研究』にも載せ、今回の東洋文庫本にも収録された。
「我国史学史上異色の文献」である、慈円の当書に対し、それが承久の変(承久三年五月)以前の著作(三浦周行説)か、それとも以後の著作(津田左右吉説)か。当時学界の対立した、当書の成立経緯論争に対し、果敢な分析と周到な「再認識」を行ったものである。そして前者を是とし、このような判断が当書のもつ歴史的意義の理解に対して、重要な史料批判上の基礎となることを論じ抜いたのであった。
わたしも、あの三カ月の普通講義において、この村岡の津田批判に接し、その語気の烈しさに驚くと共に、学究者としての清冽の気に打たれたことを生涯忘れることができない。当論文の末尾に、
「終りに、本論文にその所説を紹介した諸学者に対しては、その説に対する賛否は別として、愚管抄研究の先蹤として、深く敬意を表する」
と書かれているのは、そのまま、昭和二〇年五月講義中の、村岡のしめした語気である。
問題は、次の点だ。いかに「異色」とはいえ、しょせん渺たる一論者の一著述に対してすら、その書の「成立事情」と「内容と意義」に関して鋭い批判眼を向けた村岡が、なぜ一国の史書たる古事記・日本書紀に対して、内容としての「倫理」や「日本思想」のみを摘出して論じ、この両書の間に横たわる成立事情、そこに存在する重大な「溝」の存在に対しては一才目を向けなかったのであろうか。
宣長の場合は、村岡の論じたように、いわば「信仰的態度」によって古典(記・紀)に接するをもって基本としていた。いわば「信仰の学」である。これに対し、村岡の目ざしたところは、さにあらず。明治以降の、近代の学問であった。アウグスト・ベェクのいう「認識せられたものの再認識」の学であった。そのためには「記を捨て、紀を創った」という基本認識とその根本批判を抜きにしては、実は真のフィロロギーは成り立ちえないのではあるまいか。
ここでも、ことの「結着」を与えるのは「考古学的分布図」である。南九州には「三種の神器の分布」など、まったく存在しない。隼人塚の世界であるから、当然である。これに対し、わたしの指摘するところ(原田大六氏の先唱による)、高祖山連峯は、文字通り「三種の神器に囲繞れた地帯」なのである。
吉武高木(福岡市)・三雲(前原市)・須玖岡本(春日市)、井原(前原市)・平原(前原市)
は、あるいは“数十面の鏡”やあるいは“千余個の勾玉”や“剣”をふくみ、いずれも「三種の神器」の古墓である。そしてその淵源をなす、
吉武高木(福岡市)
は、文字通り「日向」の地に存在しているのである。博多湾にそそぐ室見川が、日向峠方面から流れてくる日向川に合流している地点である。もちろん、すべて筑紫の中の「ひなた」である。
このような考古学的分布状況を「眼前」にしても、なお多くの学者は「南九州説」という「宣長流」を権威として“叙述”しつづけている。(時として「北部九州説」に左袒する学者も、原田大六氏やわたしの名前をあえて「カット」している)。
宣長はよい。彼にとって「考古学的分布状況」など、知るよしもなかった。しかし、村岡学の場合、すでに右のような「分布状況」は、(注意すれば)現われはじめていた。たとえば、三雲と井原は江戸時代(文政と天明年内)の「発見」であり、須玖岡本は明治三二年の「発見」だったのである。
要は、次の点だ。「天孫降臨」とは、単なる“伝説”ではなかった。リアルな土地鑑をもつ「歴史伝承」そのものだった。
本居宣長は、さもあればあれ、村岡学のすすむべき、近代の学としての道は、このような「考古学的分布状況」を無視するものであってはならない。それでは「認識せられたもの」の生き証人としての、地下からの貴重な古代の発見を“知る”こととはならないであろう。すなわち「再認識」の道は断たれるのである。
一七
第一四は、「天孫降臨の出発点」である。到着点がリアルな、実在の地点ならば、「出発点」もまた、そうでないはずはない。これを明らかにしよう。その上で「考古学的分布状況」との対比を求めてみよう。
古事記の「天孫降臨」の段は「天降ります」と結ばれている。この「天降る」という術語は、古事記の神代巻の全体において、きわめて特色のある形で使用されている。すなわち、その「天降る」到着地は“筑紫”“出雲”の二領域しかない。しかも、その間(出発と到着の間)における「中間経過地」が存在しないのである。従ってその原点となる「天国」は、右の二領域の「北側」にある。わたしはそのようにみなした。
一方、古事記の中で「天の〜」と呼ばれているのは、隠岐(天之忍許呂別)から五島列島(知詞島。天之忍男)等まで、いずれも対馬海流上の島々である。すなわち、この領域が「天国」である。
右の二つの(異った方法による)検証は、同一の帰結をしめしている。いわく、
「壱岐・対馬を中心とする、対馬海流上の島々が『天国』と呼ばれている。すなわち“海人あま”の国々である。(「天」は“当て字”)」
と。
従っていわゆる「天孫降臨」の出発点は、壱岐・対馬を中心とする海上の島々であるとみなされる。
この立場からすれば、先にあげた「天孫降臨」の一節に至る、直前の文面の意義も、明快である。
「天の石位いはくらを離れ、天の八重多那雲やへたなぐもを押し分けて、伊都能知和岐和和岐弖いつのちわきちわきて、天の浮橋に宇岐士摩理うきじまり、蘇理多多斯弖そりたたして、」(以下、竺紫の……「天降ります」に至る)
右の「石位」は天照大神とニニギの居域。岩石におおわれた対馬(浅茅あそう湾岸か)の一画であろう。「伊都」は港。「雲」は“集落”。(「奇」と「藻」)「天の浮橋」は陸上と舟との間にわたす横板。現在でも、漁師たちに使用されている用語のようである。
要するに、“対馬の浅茅湾の周辺を発し、壱岐などの港々めぐり、島々から集合し、兵士たちは軍船の中にさっそうと立ち上がり、”という、「筑紫への海人あま族の侵入軍」の雄姿が活写されている。
各軍船は九州北岸部周辺の各港に上陸する。その各地からそれぞれ「同一の目的地」を目指す。それが高祖山連峯の「クシフル岳」であった。
いったん、この高地を占拠すれば、西側の菜畑や曲田の縄文水田、東側の板付の一大縄文水田、いずれもただちに「眼下」にある。それらの稲作中枢地の死命を制することができる。そういう、戦略的キー・ポイントをなす地形だったのである。
以上、従来「天上の夢幻の挿話」のように思われていた、この簡潔な一節は、古代の軍事作戦の実態を伝える、“完壁な一文”だったのであった。 ---- 史実である。
この点、最近、急速に報道が累積されているように、壱岐の原の辻一帯では、「三種の神器」の各部分(鏡や玉や剣)が次々と発見されつづけている。「天孫降臨」の出発領域として、まことにふさわしき「考古学的出土品の分布」といいえよう。(軍船の集結地は「浅茅湾」)
いわゆる「神話」は、歴史の、筋の通った背骨をもつ。その一点が、ここにも示唆されていたのである。 (6)
一八
第一五、次に述べるべきは、「民俗学的な現地伝承と記、紀神話との対応」問題である。(形式上、通し番号とする)
村岡は柳田国男の学問、いわゆる民俗学の展開に対して注意していた。敬意をもっていたともいいうるであろう。しかし、そこには「時間」がない。その要素が欠けているため、歴史学にはとり入れにくい。そのように考えていたようである。(原田隆吉氏による)
確かに、「何年、々々」といった「時間」は民俗学には存在しない。しかし、民間伝承や神社伝承の中には、明白に「記紀神話」との対応関係をもつ。そのような伝承もまた、存在するのである。その一例を挙げよう。
先に述べた、対馬の浅茅湾の東端部に、小船越がある。縄文や弥生の時期の漁船は、この地(陸上)を越えて(陸上移動)、対馬の東岸部へ出ることができたであろう。そこを南下すれば、厳原(いづはら 対馬)や原の辻(はらのつじ 壱岐)の港々に直行することができる。
その小船越に阿麻氏*留(あまてる)神社がある。その氏子代表、小田豊の(祖父から)伝承するところによれば、当地の「アマテル大神」は、年に一度出雲へ行く。神無月(旧一〇月。現一一月)である。諸神の中で“最高の神”であるから、(祭礼のはじまるまで待たずにすむように)一番最後に行く。そして祭礼が終わると、(待たずに)最初に帰ってくる、と。その月は、舟で対馬と出雲の間を往還するに(風の関係で)最良の季節である。小田はそのように語った。
記・紀伝承にいう「天照大神」は通例「アマテラスオオミカミ」と読まれているが、これは後代の「敬語読み」であり、本来は「アマテル大神」であった、と思われる。すなわち、この小船越の阿麻氏*留神社の神名と同一である。
氏*は、氏の下に一。JIS第3水準、ユニコード6C10
しかも、小田の語った神社伝承に対しては、次の点が注目される。
“神無月における、諸神の「出雲詣で」は、後代の参勤交代(江戸時代)のように、出雲の大神が中枢の主神であり、他は配下の諸神である。その「配下中のナンバー・ワン」の位置に、この「アマテル大神」は位置づけられている”。
すなわち、記・紀伝承にいう「国ゆずり神話」の“前提”の形である。
なぜなら、「出雲が主、天照が従」の形が大前提となってこそ、はじめて「国ゆずり」という“言葉”がリーズナブルとなる。一定の「意味」をもちうるのである。率直にいえば、
「出雲の大神が主人公、天照大神はその“一の家来”であった」
この概念、大義名分上のあり方である。明治以降、とくに「天照大神は、神々の中の最高神」というイメージが喧伝されつづけ、人々の心に「定着」させられてきたけれども、この(阿麻氏留神社の)現地伝承は、それに反する、それ以前の「形」を伝えていたのであった。そしてこの「形」を前提にしなければ、記・紀伝承そのものが「意味」をなさないのである。いいかえれば、記紀伝承とは、
「なぜ、ナンバー・ツーの座にあったアマテラスが、出雲の大神の占めていた『主権』を奪い、みずから『最高位』に立ちえたか」
これを解きあかし、物語るメッセージだったのである。
現地伝承を抜きにして、記・紀伝承の真実を知ることはできない。 ---- わたしたちはこの重要な命題を、ここに手にしえたのである。
もちろん、現地伝承とは、「認識せられたもの」だ。その「再認識」としての把握、それが右のように的確な史料批判をもたらしたのである。
これ、「天照大神、至上主義」を不可侵にして自明の大前提とした本居学の及びがたきところ。しかしそれをうけつぎつつ、これを「史学」として徹底し、近代に樹立せんとする村岡学にとって、必ず到るべき「約束の地」だったのではあるまいか。
一九
第一六、右に関連して「国ゆずり」それ自体を語る、現地(出雲)伝承を検証しよう。
古事記の伝えるところでは、天照大神が建御雷命を使者として出雲の大国主命に送り、主権の委譲を迫った。大国主は、ことを子どもの事代主命に託した。美保関にあった事代主は、この「天照大神の御意向」につつしんで従った、というのである。事代主は“尊貴なる天照の命に従う模範生”のようなイメージで語られている。
しかし、美保関の「現地伝承」は異なる。天照側の「侵入」をうけ、最後の決戦を行った場合、民衆に多くの犠牲の生じるのを、事代主は怖れた。その結果、自分の一身を犠牲にし、海中に身を投じた。それによって多くの「国民」(出雲と出雲側服属の民)の生命を救ったのである。この事代主の「自己犠牲と民衆に対する愛」、これを決して忘れず、記念するために行われるのが、毎年四月七日の青柴垣(あおふしがき)神事であるという。
もちろん、この神事の由来は古い。当然「弥生以前」にさかのぼる淵源をもつ神事であろう。(和歌森太郎『美保神社の研究』国書刊行会)
わたし自身、美保関に何回か足を運び、同行者(古代史研究旅行の一団)の注意をうけてはじめてこの「事代主犠牲」問題に気づいた。しかし、いったん“気づけ”ば、これを再び無視しえない、重大な「歴史の記憶」が蔵されている。「史実の鋭い針」がひそめられていたのである。
もし、記、紀伝承の伝えるところが「本来の姿」であったならば、後世の誰人が現行の現地伝承のような「形」へと“改変”しうることであろうか。考えられない。
逆に、本来はこの現地伝承のような「形」であったものを、記・紀は「勝利者となった天照側の目」の下で書いた。“書き直し”た。--- それなら、理解できるのである。すなわち、ことの進行は、
「(出雲の)現地伝承から、記・紀伝承へ」
という“変動”があったのである。決して、
「記・紀伝承から、(出雲の)現地伝承へ」
というような“変動”ではない。それは人間の理性において考えがたいのである。
この一事によってみても、もし論者が「記、紀伝承のみを尊重し、現地伝承を無視ないし軽視する」という立場を固守するならば、それは「古代の姿」をありのままに伝える、ということにはならない。決してなりえないのである。
右の比較によっても、「記・紀尊崇」に終始した本居学の限界、もしくは一大欠落点は明らかであろう。そしてそれ以上に、近代の学としての村岡学においてもまた。あらためて語る必要もなき一事なのではあるまいか。
記・紀は決して「古代そのまま」の伝承にあらず、「勝利者側の手」によって書かれ、伝えられた伝承である。この自明の事実を確認すればよい。そこに問題はおのずから判明するのである。
その上、一つの重要な注目点を挙げておこう。右のような「事代主の犠牲」を主たるテーマとする伝承自体、「活字」など公的(オフィシャル)な形では、神社側でも、必ずしも“残され”ていない。 ---- この一点だ。
すなわち、「口伝」とその上に立った「神事」の姿、そのものである。原則的に他には、ない。(美保神社の社前の“看板”には、その旨の大略が記されていた)
おそらくこれは、“偶然”ではない。ことの性格上、記、紀伝承に合わぬ、あるいは反する、このような伝承を、ことさら「記す」ことを嫌い、もっぱら「祭儀」そのものの姿、そして「口伝」によってのみこれを“保存”しようとした。----わたしには---- 根本において ----そのように思われるのである。
祭儀は、簡単である。“やつれた姿”の事代主命、それに扮(ふん)した宮人が、両脇を付き人にかかえられ、海岸に来たり、「天の浮橋」(古い横板)を越えて舟に乗る。舟は去る。 ----これで終わる。「祭」といえぬほどの、簡単な「海への道行き」である。ここに土地の民の万感がこめられている。二千余年の伝説を守りつづけ、今日に至っているのであろう。 ---- 歴史の闇は深く、認識への道はあまりにも遠いのである。しかし真の学問はそのためにこそ存在する。そしてそれは人間にとって必要にして不可欠なのである。
二〇
第一七、今、新テーマに向かおう。ここにおいて「記・紀伝承」は、もっとも幸せな一ぺージをむかえる。それは他の、著名の同時代記録の記するところと、まさに「一致」しているのである。それは、倭人伝の次の一文である。
「女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏憚す。常に伊都国に治す」
倭人伝の冒頭部において、
「一大国に至る。官をまた卑狗ひこといい、副を卑奴母離ひぬもりという」
と書かれている。壱岐島である。
従って右の「一大率」とは“壱岐(一大国)の軍団の統率者”の意とならざるをえない。すなわち、「壱岐の軍団」こそが、女王国にとっての“親衛隊”のような存在なのである。その特徴として次の二点が注目される。
(その一)諸国がこれを「畏憚」している、とある点からみれば、この「壱岐の軍団」は、“外(壱岐)からの侵略者”であり、“征圧者”である。
(その二)対馬(対海国)と壱岐(一大国)において、長官(卑狗)も、副官(卑奴母離)も“共通”している点からみると、この「壱岐の軍団」の実態は、「壱岐、対馬の共同軍団」である。彼らが“侵入”し、“征圧”して、以来、現在(三世紀)に至る「倭国」の政治的、軍事的秩序を維持している。現在の「倭国」の根幹をなす実力軍団はこの「伊都国」に存在した。
(その三)対馬は全島“岩山”からなり、“祭祀と神事の島”である。地形上、巨大な湾港である「浅茅湾」を擁し、軍船の集結すべき適地をなしている。
(その四)これに対して壱岐は、平坦であり、多くの「人口」をもつ。一般住民・武装者ともに、この地に“集中”している。「一大率」と称される由縁であろう。
(その五)これに対して「倭国の女王」たる卑弥呼(正しくは「俾弥呼 ひみか」。魏志、斉王紀。倭人伝の「卑」は略字)は、対馬の「天照アマテル大神」の権威と権力と巫女の伝説を“継承”し、これを“復活”させた存在である。
以上のように、この倭人伝の一文は、倭国の権力の基礎構造をしめすと共に、「記・紀伝承」の語っていた「天孫降臨」の真実性(リアリティ)を見事に“裏書き”していたのであった。
以上の分析は、あまりにも平明である。しかし、多くの論者はこのような指摘を行わなかった。「一大率」問題は、各論家によって、屈強の論争点となりながら、このように平明な理解をとる者をみなかった。わたし自身も、『「邪馬台国」はなかった』(一九七一)では、この解をとりえず、その「朝日文庫」版(一九九二)のあとがき「補章、二〇余年の応答」で、ようやくこの立場を採りえたのであった。 (7)
先の「一大国」と後の「一大率」を連結させて理解する。それは自然だ。だが、肝心の「記・紀伝承」の「天孫降臨」について、
(1) (戦前)天上から地上日本への降下。(超自然的理解)
(2) (戦後)「非史実」の“架空”の神話と見なす。(啓蒙主義的理解)
のいずれかに、論者の「頭」がしばられていたから、三世紀の、現実の「倭国」伝が、「天孫降臨」という史実を背景として書かれている、などとは、思いもおよばなかったのである。
その上、先述のように、本居学の影響によって、
(3) 「天孫降臨地」を南九州に当ててきた。
この点もまた、このような、きわめて平明な理解をさまたげてきた、重要な理由ではなかったのであろうか。
近年、倭人伝をもって“架空の非事実の書”であるかに“称する”論者が時として出現している。無理もない。倭人伝が同時代史料として的確であることを認めれば、必ず「天孫降臨」という(征服者側からの)美名にかかわらず、その実、民衆や一般部族にとってはまさに「畏憚」の的に他ならなかった、その史実をも認めざるをえなくなるからである。あるいは、その「予感」からかもしれぬ。それゆえ、「天孫降臨」はもとより、倭人伝もまた「信ずるに足らず」とみなす方が、現代の「国家」のために、安全なのである。しかし、それは人間の理性に反する。人間の学問の許しうる道ではない。
「古代のありのまま」をつきとめようとした本居学、その心情と真意を「了」とし、これを「よし」と見なした村岡学。それは共に、ここにしめされたような「天孫降臨」の史実性、そして「同時代史料」としての倭人伝の真実性を、男らしく、否、人間らしくうけ入れる。それ以外に、その前途はない。あらゆる日本思想史学の真の発展はありえないと思われるのである。
二一
かって紅顔の若輩、今廃残の一研究者と化している。その老漢、村岡先生の面前において行う一批言すら万死に値する。そのように評する人々もあろう。もとより、正しい。
けれども、思い出す。あの三ヵ月の最後、諸先生集いて「壮行の宴」をもよおしてくださった日のことを。学生の数より、先生の方が多い。多くの学生はすでに戦陣に向かっていたからである。
諸先生、激励の辞をのべられたあと、村岡先生は立たれた。
「フィヒテは言った。青年は情熱をもって学問を愛する、と。この四月以来、わたしはその言の真たるを知った。
諸先生方は言われた。すでに農村におもむく。勉学に心を労するなかれ、と。その心事はまことに了とすべきもの。わたしもその心事においては全く同感である。
その上において、わたしはなお告げたい。分刻を惜しんで勉学せよ、と。荻生徂徠は寸刻を惜しむべきを述べたけれども、わたしは今の時、さらに分刻を惜しんで勉学すべきである、と述べ、以て諸君に対する、わたしのはなむけの言葉としたい」
と。その言葉は今も、昨日のようにわたしの耳底に残っている。
爾来六〇年になんなんとし、すでに余生は乏しい。ここに先生の霊前において十数論をささげ、その御批正を賜わりたいと患う。
ここに列示した論点、必ずしもわたしにとって新奇の立批判言ではない。むしろ、この三十余年、述べつくし、学界に向かって問いつづけたところ、その反復にすぎない。それをあえて今、ここに集記するのはなぜか。この間、学界からは沓として、これに対する応答をみないからである。
では、学界の人々がわたしの提言を知らぬためか。残念ながら、否である。その一証をあげれば、たとえば今、京都大学内で刊行されている学生新聞において、わたしの立場に立つ歴史展開が平成六年以降、何号かおきに連載しつづけられ、すでに一〇〇回近くにおよんでいる。東京大学においてもまた、同様の連載がある。さらに九州大学ではすでに早い時期から、同趣の連載が行われていた。
すなわち、各大学の学生は、わたしの立説の存在することをよく知っている。少なくとも、知る者は少なくはない。
しかし、各大学とも「日本史」や「日本思想史」の論文において、わたしの立説については、これを「引用」せしめない。このような奇態がすでに、延々とつづいて二十数年におよんでいるのである。これが村岡先生の言われた「清き心」そして「あかき心」の表現であろうか。否、近代の学問のシンセリティ、「誠実の精神」なのであろうか。わたしには疑いなきをえず、先生の霊前において、あえてこの一文を草させていただいたのである。一言もって「学問のため」以外の何物でもない。
しかしながら、慶事がある。新来の研究者がきびすを接して現われ、次々と、わたしなどの予想もできなかった局面の諸論文を公表していることである。
たとえば今号(第八集)にも掲載されると聞く、古賀達也氏の「二倍年暦」論なども、その一例である。耳にするだけでも、わたしの思いおよばぬ世界へと学問的仮説の輪をひろげられている。
その成否は、わたしの能力を越えるものであるから、「当否知らず」と答える他はない。ないけれども、言うことができる。学問上の一仮説を立て、論理をもってこれを一貫する。それこそが学間である、と。その当否は、後代万人の審判するところとなろう。
この点、「日本と世界」「古代と現代」と、対象は変わっても、向かうべき学間の精神はもとより同一の精神、同一の論理なのである。
村岡先生の思想史学も、一方では上代、他方では中世、また近世の司馬江漢や明治維新期の平田学派に至るまで、立論のとどこおるところとてなかった。まさに博論である。その立つところ、同じき学問の精神に依拠されたからであろう。わたしなどの遠くおよばぬところである。
しかしながら、このような若き研究者 ---- たとえば、二〇代前半の研究者などもまた、立ち現われている。 ---- の今日の簇立を喜びたい。のみならず、さらに八○代のすぐれた研究者さえ現れている。
この上は己が死に至るまで探究の道を歩み、ある日忽然とその日を迎える。ときあっていかに老醜をさらそうとも、なんら意に介するところではない。
必ず村岡先生の面前に坐し、限りなくその御叱正に浴する日々を無上の喜びとするであろう。
---- 二〇〇四年、七月三日朝、擱筆
《注》
(1)現古河市(宮城県)
(2)田中卓「神功皇后をめぐる記・紀の所伝 -- 特に神功皇后紀の成立について」(『神功皇后』神功皇后論文集刊行会編、昭和四七年)
この田中論文には、従来の「神功紀の成立論」や「卑弥呼と神功皇后の比定論」「日本書紀の紀年と神功紀」に関する諸論文が詳しく紹介されている。
(3)「倭の女王」は北野本では「貴倭の女王」(傍点、古田 インターネット上は赤色表示。)となっている。底本(天理図書館蔵、ト部兼右本)の「傍書イ」も同じ。(岩波、日本古典文学大系本、校異)--- 注目すべきである。
(4)この句のあとは、従来「倭国の極南界なり。光武、賜うに印綬を以てす」(岩波文庫)と読まれてきたが、正しくない。これは、
「倭国の南界を極むる也や、光武賜うに印綬を以てす」
である。「南界」は後漢書倭伝中の、
「朱儒より東南船を行やること一年、裸国・黒歯国に至る。使駅の伝うる所ここに極まる」
などの「倭国情報」を指しているものであろう。「奴な国」が倭国の「極南界」にある、という地理認識など、およそありえないのである。
(古田「学問の未来」昭和薬科大学文化史研究室、一九九六年三月、「7・極南界」)
(5)当初「白村江の戦」以後の築造説があったが、勝利者の唐軍が筑紫にくりかえし「進駐」している中で、ありえない(「水城」も同じ)。
その後、六〜七世紀の築造とみられてきたけれど、諸種の科学測定に“目を背け”ない限り、「四〜五世紀」頃へさかのぼることは、避けえないのではあるまいか。
特に、匈奴・鮮卑側が西晋朝を亡ぼし、洛陽や西安を征圧して「北朝」を樹立した「三一六年」以降、魏・西晋朝に“服属”してきた「倭国」が、なんらの防塞軍事施設を設けないことなど、およそ考えられないのである。「対、高句麗・新羅」の防塞機構である。
近年、もっとも新しい「神籠石」として、唐原(福岡県)の発掘がすすんでいる。それは中心的礎石を点々と置いたまま、中断された形をしめしているという。白村江の敗戦まで、“作りつづけ”られていたことをしめす。「六六二」である。
四世紀中葉から七世紀中葉に至る「神籠石群の編年」が、今後の重要な研究課題となろう。
なお、唐原の場合、瀬戸内海に臨む、福岡県の「東端部」であるから、ただ“北方の敵”たる唐や新羅に相対するだけではなく、“東方の敵”(近畿方面)をも意識していた可能性があろう。今後の興味深い課題である。
(6)古田「日本軍事史の原点 -- 天孫降臨」(多元No.50、二〇〇二年、六月)
(7)角田彰男『邪馬台国五文字の謎』(移動教育出版事務局、平成一五年七月。(壱岐中心史観に立つ)
これは研究誌の公開です。史料批判は、『新・古代学』各号と引用文献を確認してお願いいたします。
新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから
Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“