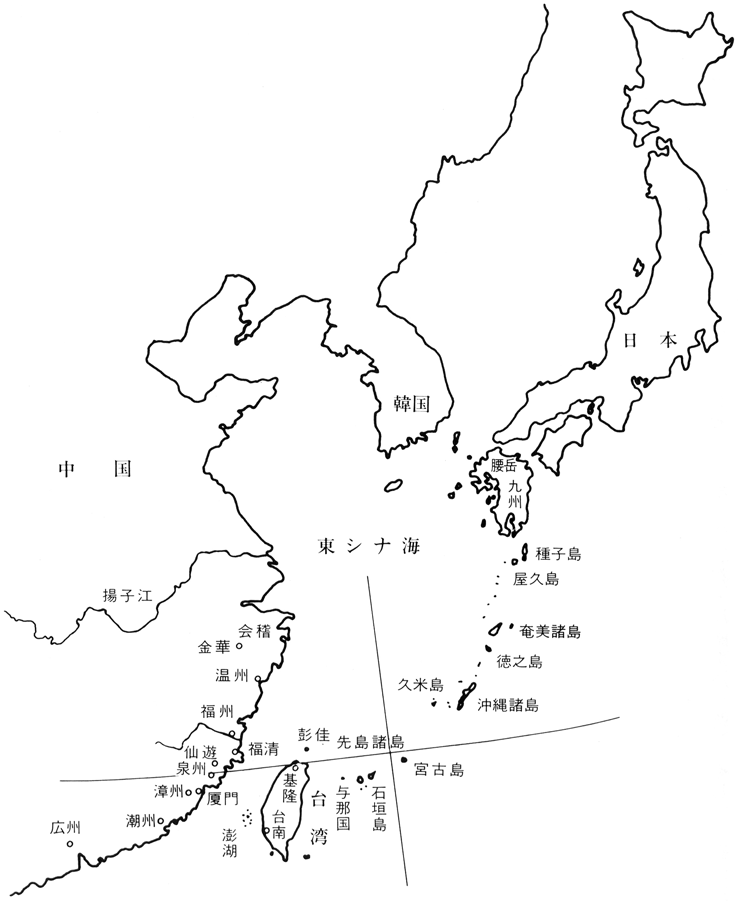
増田修
流求の名があらわれる最古の文献史料は『隋書』である。『隋書』の帝紀・列伝は唐の貞観一〇(六三六)年魏徴の主編により成り、志は顕慶元(六五六)年長孫無忌が監修して成った。流求についての記事は、煬帝紀上(巻三・帝紀第三、大業三年三月癸丑条・大業六年二月乙巳条)、食貨志(巻二四・志第一九、煬帝即位条)、陳稜伝(巻六四・列伝第二九)、流求国伝(巻八一・列伝第四六・東夷)の四ヵ所にみえる。
『隋書』流求国伝は、「流求国は海島の中に居す。建安郡の東に当り、水行五日にして至る」という方位・行程記事ではじまる。
わが国においては、この琉求とは、流球国最初の歴史書『中山世鑑』(羽地朝秀、慶安三年・一六五〇)をはじめとして、琉球(現在の沖縄)であると考えられ、誰人もこれを疑うことはなかった。
ところが、明治七(一八七四)年フランス人サン・デニーが、『文献通考』(元・馬端臨、延祐四年・一三一七)四裔考の一部を翻訳し、その琉球条を根拠にして、隋代の流求とは台湾・琉球を含む島彙の総称であるが、『隋書』の流求は台湾であるという説を発表し、流求=沖縄という通念はゆらぎはじめた。ついで、明治二八(一八九五)年オランダ人グスタフ・シュレーゲルは、元代以前の琉球は今の台湾に限り、明(みん)初にはじめてその名がいまの琉球に遷ったという説を発表した。そして、明治三〇(一八九七)年文科大学(現在の東京大学)史学科教授ドイツ人ルードヴィヒ・リースが『台湾島史』(吉国藤吉訳、一八九八)を著わし、サン・デニーの説を踏襲して以来、わが国の学会においては、流求=台湾説が定説の地位を獲得した。(1)
朱寛・陳稜らが遠征した流求について、台湾説をとる者は、その他、箭内亙(2)、藤田豊八(3)(4)、鈴村譲(5)、市村讚*次郎(6)、和田清(7)(8)、伊能嘉矩(9)〜(11)、幣原担(12)〜(15)、曽我部静雄(16)〜(17)、白鳥庫吉(18)、甲野勇(19)、加藤三吾(20)、東恩納寛惇(21)〜(24)、種村保三郎(25)、宮良當壮(26)、桑田六郎(27)、国分直一(28)、金関丈夫(29)、李家正文(30)らで、多数派を形成している。
市村讚*次郎氏の讚*は、言偏の代わり王編。JIS第3水準、ユニコード74DA
台湾説の論拠は、水行五日では沖縄には到達できない、『文献通考』などに流求は「彭湖と煙火相い望む」とあるように台湾をさす、風俗・産物・動植物相などの記述は台湾であることをしめす、というものである。
これにたいして、沖縄説を唱えるのは、中馬庚(31)〜(32)、隈本繁吉(32)、秋山謙三(33)〜(35)、喜田貞吉(36)(37)、フランス人アグノエル(38)、藤田元春(39)、台湾人梁嘉彬(40)(42)、松本雅明(43)(46)、比嘉春潮(47)、川越泰博(48)、本位田菊士(49)、森浩一(50)、古田武彦(51)、村井章介(52) らである。
沖縄説は、沖縄は建安郡の東にあたり水行五日で到達できる、『隋書』には、流求は「彭湖と煙火相い望む」という記述はない、風俗・産物・動植物相なども隋代の沖縄のものと考えることは可能である、という。
伊波普猷は、最初沖縄説(53)をとっていたが、東恩納寛惇の批判を受けて、『隋書』流求国伝における二回の流求遠征のうち、前の遠征隊(朱寛)が訪問したのは台湾で、後の遠征隊(陳稜)が征伐した流求は沖縄である、と折衷説(54)をとるに至った。
流求=台湾説に対して、戦前全面的に沖縄説を展開し、台湾説を批判したのが秋山謙三である。そして、戦後は梁嘉彬が沖縄説の論拠を深化させ、台湾説を徹底的に批判した。
しかし、論争は、いまだに帰結をみない状況にあるという。(55)(56)(57) しかも、「『隋書』の記事には部分的に伝聞の誤り、或は誇張があるとはいえ、基本的には現在の沖縄本島を対象としているとみる見解が有力になりつつある(58)」とする者がいる一方で、「論争史を整理すると台湾説が有力であるが、しかし、この問題はなお学界に残された検討課題である(59)」とみる者がいるように、どちらの説が有力かの判断がわかれるくらい、形勢は混沌としているかのようである。
そこで、唐・宋・元・明代に編纂された中国の正史・政書・類書・地理書などを中心に、流求に関する記録を繙(ひもとく)とともに、台湾説・沖縄説の各論拠を再検討してみた。
その結果、『隋書』の流求は、沖縄そのものをさしていることは確実であると判断するに至ったので、その根拠を報告しよう。
『隋書』の流求を沖縄とみるか、台湾とするかについて、核心をなす論争点は、流求国伝の「流求国居海島之中、当建安郡東、水行五日而至」という記事の方位と行程の解釈にある。
隋代の建安郡は、現在の福建省に該当する。隋初には泉州といったが、大業初年[門/虫]州とされ、さらに改めて建安郡となった。そして、大業初年[門/虫]県(現在の福州)に建安郡(郡治)が置かれた(『隋書』巻三一・志第二六・地理下)。
[門/虫]は、門の中に虫。JIS第3水準、ユニコード95A9
この流求国伝にいう建安郡は、方位・行程の基点となる、建安郡治をさすと考えられる。すなわち、南北に数百キロにわたって伸びる建安郡の海岸線のどこから出航しても、東に水行五日というのでは、その到達地点は特定できないからである。
建安郡治は、北緯二六度に位置する現在の福州の地であるから、まさにその東は沖縄本島にあたる。
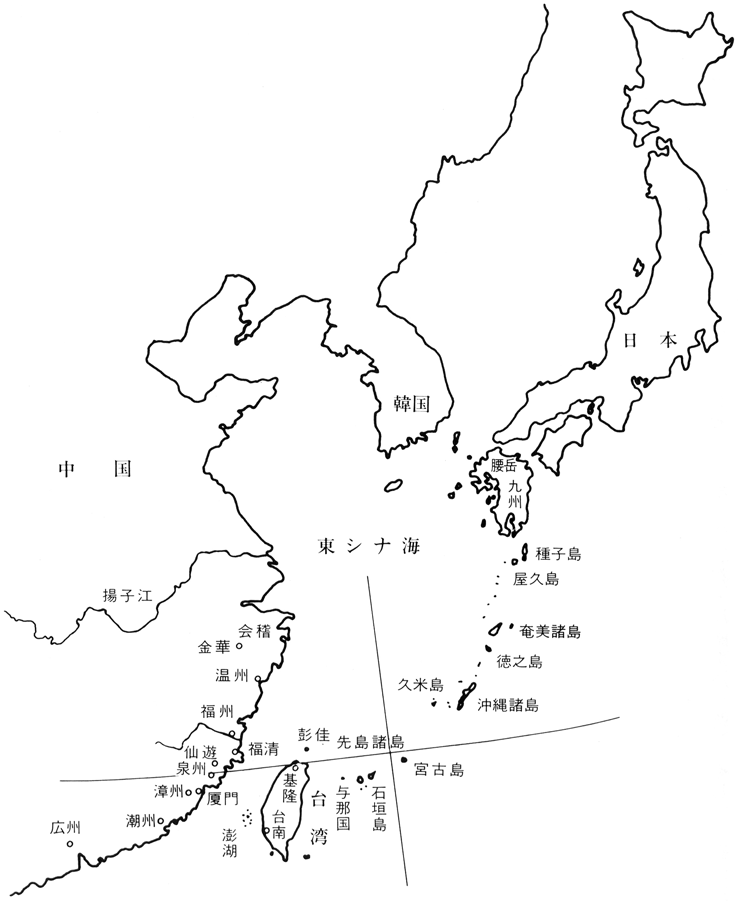
唐の顕慶四(六五九)年に成立した『北史』は、魏書・北斎書・北周書・隋書を基本資料としているので、その流求国伝(巻九四・列伝第八二)は「流求国居海島、当建安郡東、水行五日而至」と、冒頭部分から『隋書』流求国伝とほとんど同文である。
ところが、唐の貞元一七(八〇一)年に編纂された『通典』(杜佑撰)琉球条(巻一八六・辺防二・東夷下)には、「琉球自隋聞焉、居海島之中、当建安郡東[門/虫]川之東、水行五日而至」とある。『通典』は、黄帝・唐虞より唐の天宝年間(七四二〜七五六)に至るまでの中国歴代典章制度についての政書である。その琉球条は、『隋書』流求国伝を節略したものであるが、「建安郡東」に「[門/虫]川之東」、「義安」に「今潮陽郡」と二ヵ所に、新たに割注を付しているのである。そして、倭国条(巻一八五・辺防一・東夷下)には、「其国界、東西五月行、南北三月行、各至於海、大較在会稽[門/虫]川之東」とある。すなわち、『隋書』イ妥国伝(巻八一・列伝第四六・東夷)の「其国境、東西五月行、南北三月行、各至海」に「大較在会稽 [門/虫]川之東」という方位を付加している。
梁嘉彬は、[門/虫]川とは[門/虫]江をさすという。[門/虫]江は、建安郡治(現在の福州)を流れて、東シナ海に注ぐ川である。そうすると、[門/虫]川の東にあたる流求は、沖縄であって台湾ではない。
ここで注目すべきは、『通典』が、倭国の位置を「大較在会稽[門/虫]川之東」としている点である。倭国は、大業四(六〇八)年階の煬帝が文林郎裴世清を派遣し、不遜にも日出ずる処の天子と称した国王天の多利思北孤の実情を調査させたところである(『隋書』巻八一・列伝第四六・東夷イ妥国)。その裴世清は、隋滅亡後唐朝の正規の外交官僚である鴻櫨寺の掌客に任用されている。(51)(60) 倭国はまた、貞観五(六三一)年唐の太宗が新州刺史高表仁を派遣し慰撫させたが、その王子が無礼にも礼を争い、表仁は朝命を宣べることもできずに還った国である(『旧唐書』巻一九九上・列伝第一四九・東夷・倭国)。そして、『日本書紀』によると、天智二(六六三)年八月ついに、倭国・百済の連合軍は唐軍と白村江に会戦したが完敗し、唐は朝散大夫上柱国郭務宗等を五度倭国に派遣し、戦後処理をおこなわせている。(61) 『通典』倭国条にも、倭は一名日本国というとして、朝臣(粟田)真人と朝臣(阿部)仲満が来朝したことが記録されている。
このように、外交・軍事行動の対象であった倭国の地理的位置を、『通典』は「大較会稽[門/虫]川の東に在り」というのである。それと同時に『通典』は、その倭国の方位である「会稽[門/虫]川の東」と重なるように、琉球国は「[門/虫]川の東」にあたるという。したがって、その琉球が沖縄をさすことは必至であって、台湾ではないことは明白であろう。『太平御覧』(宋・李[日方]等撰、太平興国二〜八年・九七七〜九八三)流求条(巻七八四・四夷部五・東夷五)にも、「陰ママ書曰、流求国居海島之間、当見建安郡東、水行五日而至 [門/虫]川之東也」とあり、流求の方位は「[門/虫]川の東」であるとされている。
李[日方]の[日方]は、日に方。JIS第3水準、ユニコード6609
イ妥(たい)国のイ妥*は、人偏に妥。ユニコード番号4FCO
『太平寰宇(かんう)記』(楽史等撰)は、宋の太宗が、太平興国四(九七九)年[門/虫]越・北漢を併合して全国統一を果たすと、その境域・外民族の事情を明らかにするために、編纂を命じた地理書である。その琉球条(第一七五巻・四夷四・東夷四)は、『隋書』流求国伝をやや簡略化し改編したものであるが、温州条の四至八到中にも琉球国があらわれる。
江南東道の各州の四至八到のうち、琉球の方位に関係があるものをみると、つぎのようになっている。温州の四至八到、「東至大海八十六里海以外是琉球国(注、宋版は幽求国(41) )、南至福州水路相承一千八百里」(第九九巻・江南道一一)。福州の四至八到、「東北至温州水路一千四百七十八里、南至泉州三百七十里、東南至海一百六十四里、西南至泉州五百里」(第一〇〇巻・江南東道一二)。泉州の四至八到、「東北至福州五百里、東至大海一百八十里、東南至海四十里、西南至樟*州六百里」(第一〇二巻・江南東道一四)。樟*州の四至八到、「東北至泉州六百里、東至大海一百五十里、南至大海一百六十二里、西至潮州五百六十里」(第一〇二巻・江南東道一四)。そして、嶺南道の潮州の四至八到も、「東至樟*州七百五十里、東南至海口九十里、東至大海一百里、東北至汀州魚磯鎮六百五十里」(第一五八巻・嶺南道二)という。
樟*州の樟*は、木編の代わりに三水編。JIS第3水準、ユニコード6F33
すなわち、『太平寰宇記』は、温州の東の大海の外に琉球国があるという。温州は、北緯二八度線上に位置し、その東方はかつての琉球王国の領域であった奄美大島である。そして、福州・泉州・樟*州・潮州の東と東南は、たんに海があるだけで、その海外に琉球国はおろか、膨湖島や台湾に該当する島々の存在を告げることはない。『太平寰宇記』の江南東道の四至八到は、温州の東の海外にあるという琉球国が沖縄であることをしめすとともに、北宋の初めころには温州が琉球との交通の基点となっていたことを知らせてくれる。そのころは、いまだ中国と澎湖島・台湾との間の航路は開かれていなかったのである。「沖縄本島、および先島諸島諸地域から、いわゆる宋磁の類の出土がおびただしく、石垣島名護湾では、現在でも多くの宋磁破片が波に洗われつつ打ち上げられている(62)(63)」というが、北宋代の磁器は、温州から船積みされたものであろう。
『隋書』には、流求国伝冒頭の「流求国は海島の中に居す。建安郡の東に当り、水行五日にして至る」という方位・行程記事のほかに、行程をしめすつぎのような記事がある。
「帝(煬帝)、武賁郎将陳稜・朝請大夫張鎮州を遣わし、兵を率いて、義安より海に浮んで之を撃たしむ。高華嶼に至り、又東行二日にして![]() に至り、又一日にして便(すなわち)流求に至る。初め、稜(陳稜)は、南方諸国人を将(ひき)いて従軍せしむ」(流求国伝)。
に至り、又一日にして便(すなわち)流求に至る。初め、稜(陳稜)は、南方諸国人を将(ひき)いて従軍せしむ」(流求国伝)。
「陳稜、・・・大業三年武賁郎将を拝す。後三歳、朝請大夫張鎮周と東陽を発す、兵万余人。義安より海に汎(うか)び、流求国を撃つ。月余にして至る」(陳稜伝)。
![]() [句/黽][辟/黽]嶼は、句の下に黽。辟の下に黽。(亀に似た形から、久米島と考えられる。後記)
[句/黽][辟/黽]嶼は、句の下に黽。辟の下に黽。(亀に似た形から、久米島と考えられる。後記)
台湾説は、義安(現在の広東省潮州)から出航したのであるから、すぐ目の前の台湾を撃ったという。そして、台湾説は、高華嶼と![]() を澎湖列島内の二島にあてる。しかし、澎湖列島内で東行二日は過大だし、方位も不自然である。
を澎湖列島内の二島にあてる。しかし、澎湖列島内で東行二日は過大だし、方位も不自然である。
むしろ、これらの記事は、陳稜が東陽(現在の浙江省金華)から出兵し、南下して義安(潮州)に至り、そこで南方諸国人を戦力として補充し、糧食・飲料を補給し、大艦隊を編成したうえで、義安から出航したので、流求まで一カ月余かかったことを示している。陳稜の水軍は、義安から北上して、航行の目標としている高華嶼に至り、「又東行二日にして![]() に至り、又一日にして便ち流求に至る」のである。
に至り、又一日にして便ち流求に至る」のである。
高華嶼から![]() を経て流求に至る三日は、建安郡治から出発して流求に至る五日の行程のうちの後半の三日の行程に該当する。これを裏付ける行程記事が、『新唐書』(宋・欧陽脩等撰、嘉祐五年・一〇六〇)にある。
を経て流求に至る三日は、建安郡治から出発して流求に至る五日の行程のうちの後半の三日の行程に該当する。これを裏付ける行程記事が、『新唐書』(宋・欧陽脩等撰、嘉祐五年・一〇六〇)にある。
『新唐書』には、『旧唐書』(後晋・劉[日句]等撰、開運二年・九四五)と同じく、流求国伝はない。しかし、『新唐書』地理志(巻四一・志第三一・地理五)の「泉州清源郡」の細注には、「自州正東海行二日至高華嶼、又二日至![]() 、又一日至流求国」という方位・行程記事が存在する。
、又一日至流求国」という方位・行程記事が存在する。
劉[日句]の[日句]は、JIS第3水準、ユニコード662B
隋の建安郡は、唐初にはふたたび泉州となった。そして、景雲二(七一一)年南部の三県を分けて泉州、北部を福州と二分割した。この泉州は、天宝三(七四二)年から乾元元(七五八年)の間は泉州清源郡と称したが、その後また泉州となり、晋江県(現在の泉州)に州治を置いた(『旧唐書』巻四〇・志第二〇・地理三・江南道)。この泉州は、宋代の泉州(現在の泉州)へとつながっている。
そこで、梁嘉彬は、『新唐書』地理志の流求国に至る方位・行程の細注は、隋代の泉州・建安郡治が編入されている「福州長楽郡」の条に起すべきところを、宋代の執筆者が錯簡して、宋代の泉州に該当する「泉州清源郡」の条に起したという。しかし、そうではなくても、右の細注は、宋代の泉州から流求(現在の沖縄)に至る水行記録としても解釈できるという。(42)
現在の泉州は、北緯二五度に位置し、その正東は台湾西北端(その東は、琉球列島の南端の先島諸島)であるが、泉州と台湾の間には、「正東、海行二日にして至る」高華島や、「又二日にして至る」![]() ような島々はない。
ような島々はない。
泉州から東に向って出帆すれば、明・清代の冊封便が福州から西南風に乗って琉球に向ったときと同じく、風向きと潮流によってやや東北寄りの進路となり、二日で高華嶼(台湾基隆港外の彭佳嶼であろう)に至り、さらに東行二日で![]() (亀に似た形から、久米島と考えられる)に至り、また一日で流求(沖縄)に至ることができる。
(亀に似た形から、久米島と考えられる)に至り、また一日で流求(沖縄)に至ることができる。
つぎに、流求=台湾説は、明代の記録によると、「福州梅花所開洋、順風七晝夜、始可至琉球」(明・陳侃『嘉靖甲午使録』群書質異・「羸*蟲録」、一五三四)とか、「琉球国居海中、直福建泉州之東、自長楽梅花所開洋風利、可七晝夜至」(明・陳仁錫編『皇明世法録』巻八○・琉球、崇禎四年、一六三〇)とか、あるいは「長楽梅花所開洋、南風順利、十八日可至」(明・何喬遠編『[門/虫]書』巻一四六・島夷志、崇禎四年)とあって、琉球は順風でも七日から一八日かかる遠方にあり、隋代に五日で行けるのはヨリ近い台湾であるという。
羸*は、羊の代わりに女。JIS第4水準、ユニコード5B34
ところで、清の徐葆光は、康煕五八(一七一九)年冊封琉球国王(尚敬)副使として琉球に派遣され、『中山伝信録』(康煕六〇年・一七二一)という使録を出版している。(64) 『中山伝信録』は、琉球をよく観察し従来の使録の誤りを正すなど、その記録が正確であるというだけではなく、琉球の風土・民俗を生き生きと描き出した名著で、中国や日本の琉球観の形成に大きな影響を与えている。
『中山伝信録』には、「歴代封舟渡海日期」という項目があり、嘉靖一三(一五三四)年の陳侃(ちんかん)使録から康煕二二(一六八三)年の汪楫(おうしゅう)使録に至る七回の渡海記録が収録されている。それによると、冊封使の船は、通常は夏至ののち西南風に乗って琉球へ行き、冬至ののちに東北風に乗って福州へ帰るが、最長一九日・最短三日・平均一二日を要している。徐葆光の船は、往路七日八夜、復路一四昼夜の航海であった。
梁嘉彬は、それらの渡海記録を各使録にもとづいて分析したところ、無風・逆風・台風などのため進むことができなかった日数や、卯針(正東針)を偏用するために、船が沖縄本島の北方海域に流されて、那覇に引返すのに要した日数を差引くと、すべて実日数水行四〜五日で福州と琉球間を航行しているという。(41)(42)
琉球人程順則が著した『指南広義』(康煕四七年・一七〇八)では、往路の福州五虎門から姑米山(久米島)まで四○更(四日)、復路の姑米山から福州定海に着くのに五〇更(五日)の航路である。
昭和六三(一九八八)年沖縄県ヨット連盟・東江会長一行は、ヨットによる「中国那覇間の進貢船航海を再現する試み」の渡航実験をおこなった。明・清代の琉球から中国への進貢船のルートにほぼそつた往復航行が、八月八日から八月二〇日にかけておこなわれた。その結果は、「この一行の要した時間は、往路(那覇〜福州)・帰路(泉州〜那覇)とも三日で、往時の冊封船や進貢船が要した日数より一日速かった (65)」。その原因は、帆や船体構造に差異があることと、一行のヨット航行の際には台風や低気圧が発生したので、その情報を的確に受信し、強い周辺風を利用しながら航海することができたからであるという。
それでは、中国大陸と台湾間の航海は、何日かかるのであろうか。梁嘉彬は、清初には厦門から水程わずか一一更(約一昼夜)で台湾(台南)に至り、鶏籠淡水から福州港口まで水程五〜七更であったという。前記の冊封使の渡海記録でも、福州から台湾北部海面までは、一日ないし二日の水程である。また、明の鄭成功の水師は、台湾から澎湖島に四更、澎湖島から金門へ七更(一更は約六〇里、一〇更で約一日)で達したという。
『隋書』流求は、方位・行程からみるとき、現在の沖縄であることを否定できないのではないだろうか。
元朝が、流求国の所在について持っていた知識は、曖昧模糊としたものであった。『元史』(明・宋濂等撰、洪武二年・一三六九)瑠求伝(巻二一〇・列伝巻第九七・外夷三)は、そのあり様をつぎのように伝えている。
世祖至元二十八(一二九一)年九月、海[舟工]副万戸楊祥、請いて六千の軍を以て、往きて之を降し、命を聴かずんば、則ち遂に之を伐たんとす。・・・冬十月、乃ち楊祥に命じて宣撫使に充てて金符を給し、呉志斗は礼部員外郎、阮鑒は兵部員外郎として、並びに銀符を給し、往きて瑠求に使せしむ。
(至元)二十九年三月二十九日、汀路(現在の福建省長汀)の尾澳(金門湾口か)自り舟にて行く。是の日巳の時に至りて、海洋中の正東に、山の長く而して低き者有るを望見す。約五十里を去れり。祥(楊祥)称す、「是れ瑠求国なり」と。鑒(阮鑒)称す、「的否を知らざるなり」と。祥、・・・軍官劉閏等二百余人をして、小舟十一艘を以て、軍器を載せ、三嶼人陳[火軍]を領して岸に登らしむ。岸上の人衆、三嶼人の語を暁(あきらか)にせず、其の殺死せらるる者三人なれば、遂に還る。四月二日、彭湖に至る。祥、鑒・志斗の、巳に瑠求に文字を到さんとするも、二人の従わざるを責む。明日、志斗の蹤跡、之を[木/見](もとむ)るも、有る無き也。先に、志斗、嘗つて斥けて言う、「祥の事を生ずるは、功を要(もと)めて、冨貴を取らんと欲するのみ。其の言の誕妄にして信じ難し」と。是に至りて、祥の之を害せしことを疑う。
[舟工]は、舟に工。JIS第4水準、ユニコード8221
陳[火軍]の[火軍]は、JIS第3水準、ユニコード7147
[木/見](もとむ)るの[木/見]は、JIS第3水準、ユニコード8994
そして、元の延祐四(一三一七)年に成った『文献通考』(馬端臨撰)は、琉球国は彭湖と煙火相い望むとし、流求と台湾を混同した最初の文献となった。『文献通考』は、古代から天宝年間(七四二〜七五六)までは、『通典』にならいながら増補し、南宋の嘉定末(一二二四)年までの諸制度を記した政書であるが、馬端臨の文名は高く、その影響力は大きかった。
馬端臨は、『北史』流求国伝の『流求国居海島、当建安郡東、水行五日而至」という文章と、『諸蕃志』流求国条の「流求国当泉州之東、舟行約五六日程」、および[田比]舎耶国条の「泉(泉州)有海島、曰彭湖、隷晋江県、与其国密邇(きわめてちかし)、煙火相望」という文章を交ぜ合わせて、『文献通考』琉球条の「琉球国居海島、在泉州之東、有島彭湖、煙火相望、水行五日而至」(巻三二七・四裔考四)とした、(41)・・・と梁嘉彬はいう。
『文献通考』琉球条は、『北史』流求国伝の引用からはじまるが、それに加えて、琉球は彭湖と煙火相い望むとしている。そして、『北史』の引用部分につづけて、琉球国の旁には[田比]舎耶国があるとし、『諸蕃志』[田比]舎耶国条から、宋の淳煕年間(一一七四〜一一八九)に国の酋豪が泉州の村々を襲撃した事件を引抜いて、琉球条に付加しているのである。したがって、[田比]舎耶国条は、別条として立てていない。
[田比]舎耶国の[田比]はJIS第3水準、ユニコード6BD7
すなわち、『文献通考』の琉球条は、『北史』の流求国条と、『諸蕃志』の[田比]舎耶国条の一部から、合成されている。そして、『文献通考』は、『隋書』の流求を、彭湖と煙火相い望むほど近い、台湾であると考えているのである。また、[田比]舎耶国は、琉球の旁にあるとしているので、台湾の近くのフィリピン群島中の島を想定していると思われる。
『諸蕃志(66)』は、南宋の宝慶元(一二二五)年趙汝這*が泉州の提挙福建路市舶(市舶司の長官)であったときに撰述したものであるが、『嶺外代答』(南宋・周去非撰、乾道八年〜淳煕五年頃・一一七二〜一一七八)などの記事と、彼自身が泉州に来往した外国商人達から見聞したことをもとに、諸外国の風物を記した地志である。『諸蕃志』・『嶺外代答』ともに原本は散佚して伝わらないが、『永楽大典』(明・解縉等撰、永楽六年・一四〇八)所引の佚文が集められている。現在の『諸蕃志』は、流求国条と[田比]舎耶国条(67)が、各別に立っている。そして、流求国条の内容は、『通典』に依拠し、それに新たな知見が付加され、末尾が「旁有[田比]舎耶談馬顔等国」の文句で終っている。流求国条につづいて、[田比]舎耶国条が立てられており、その国は彭湖島の煙火が望見できるほど近いという。すなわち、『諸蕃志』の流求は、『隋書』の流求と同一国であり、その旁に[田比]舎耶国があるという。その[田比]舎耶国は、彭湖と煙火相い望むのであるから、当然台湾をさしている。
迫*は、白の代わりに舌。JIS第4水準、ユニコード9002
これにたいして、金関丈夫は、馬端臨が、『文献通考』琉球条の冒頭部分に、『諸蕃志』[田比]舎耶国条の「島有り彭湖という、煙火相い望む」という文字を勝手に移したようにみえるが、そうではないという。金関は、「この大典(永楽大典)の杜撰なことは古来定評があり、『諸蕃志』の『隋書』を引用する部分のごときも、甚だ解すべきからざる疎漏さであるのは、恐らく大典編纂者の省略によるものと思われる。流求国の章の後に、[田比]舎耶国を別章として取扱ったのも、大典編纂者の誤解より生じた杜撰な仕事の一つではなかったのか。『永楽大典』の編纂者より以前に『諸蕃志』を見た馬端臨が、[田比]舎耶国の別章を設けず、『諸蕃志』のその記事を「琉球」の中に収めているのは、それが『諸蕃志』の原形であったことを示すものに他ならない (29) 」という。
しかし、現在の『諸蕃志』流求条に「島有り彭湖と曰う、煙火相い望む」という文章がない理由を、『永楽大典』編纂者の誤解や杜撰さに求めるのは、具体性のない一般論であって、説得力に欠けている。
そもそも、『隋書』およびそれにつづく『北史』『通典』『太平御覧』『太平寰宇記』『冊府元亀』(宋・王欽若等撰、大中祥符六年・一〇一三)『通志』(南宋・鄭椎撰、一一〇四〜一一六〇)の流求国に関する記事には、「有島曰彭湖、煙火相望」という文字は存在しないし、その内容も『隋書』と基本的に同じである。
馬端臨の『文献通考』につづいて、流求と台湾を混同した文献が、つぎつぎとあらわれた。
『宋史』(元・脱脱等撰、至正五年・一三四五)流求国伝(巻四九一・列伝巻第二五〇・外国七)は、「流求国は泉州の東に在りて、海東に有り。彭湖にて烟火相い望むと曰う」とし、『諸蕃志』流求国条の約三割と[田比]舎耶国条の約七割を切り取って、その内容に充当している。
『島夷誌略』(元・汪大淵撰、至正九年・一三四九)は、彭湖条のつぎに琉球条を立て、「大崎山極高峻、自彭湖望之、余登此山」と記述し、その内容も『隋書』流求国伝とはまったく異なり、明らかに台湾をさしている。しかも、[田比]舎耶国条も別に立てている。
しかし、明の洪武二(一三六九)年に成立した『元史』(宋濂等撰)瑠求伝(巻二一〇・列伝巻第九七・外夷三)は、「瑠求は、南海の東、樟*・泉・興(現在の福建省甫田)・福の四州の界内に在り。彭湖の諸島は瑠求と相対するも、亦た素より通ぜず、・・・漢唐より以来、史の載せざる所なり。近代の諸蕃の其の国に至るを聞かず」と記述し、元代の瑠求は『隋書』の流求と異なる国としている。
そして、明の太祖朱元璋は、洪武五(一三七二)年行人楊載を、瑠求ではなく、今の沖縄である琉球に派遣している。太祖の招諭を受けた中山王察度は、弟泰期を遣わし、臣と称して表を奉り方物を貢し、その後太祖から琉球国中山王に封ぜられた。
明朝は、『元史』を編纂するころには、元朝が瑠求と考えていたのは今の台湾で、『隋書』以来の流求は今の沖縄であることを知っていたので、琉球国と国交を結ぶことができたのである。
樟*州の樟*は、木編の代わりに三水編。JIS第3水準、ユニコード6F33
『隋書』流求国伝にはまた、つぎのような流求の方位と距離に触れた記事がある。
「大業元(六〇五)年、海師何蛮等、春秋二時毎に、天清く風静かに、東望するに、依希(いき)として煙霧の気有るに似たり。亦幾千里なるを知らず。」
和田清は、この記事を根拠に、福建の近海から遠望できる横亙(わたり)数千里におよぶ大島が台湾であって、それ以外ではありえないという。(8)
しかし、何蛮らは「煙霧の気有るに似たり」というだけで、流求がみえるとは述べていない。また、「幾千里なるを知らず」というのも、流求までの距離をさし、流求の横幅が数千里という意味ではあるまい。そして、福州から台湾への距離は、数百里であって桁が違う。
むしろ、この記事は、「煬帝即位するや、能く絶域に通ずる者を募る」(『隋書』巻八二・列伝第四七・南蛮・赤土)というのに対応して、大業三(六〇七)年屯田主事常駿・虞部主事王君政等が赤土国に遣使されるよう請うたのと、軌を一にするものであろう。すなわち、海師何蛮は、建安郡の東方海上に流求国があることを聞き知っていたので、煬帝に申し出たのではないだろうか。
煬帝は、中華思想の発現として、外蕃を撫慰してその臣下に加えるという伝統的な思考のもとに、未知の国流求に使者を派遣することにしたと思われる。(68)
その結果は、「(大業)三(六〇七)年、羽騎尉朱寛をして海に入り、異俗を求訪せしむ。何蛮之を言う。遂に蛮と倶(とも)に往き、因りて流求国に到る。言相い通ぜず。一人を掠(かすめ)て返る。明(六〇八)年、帝復(また)、寛(朱寛)をして之を慰撫せしむ。流求従わず。寛、其の布甲を取りて還る。時にイ妥国の使来朝す。之を見て曰く『之れ、夷邪久国人の用うる所なり』と」(流求国伝)ということになったのである。
そして、煬帝は、流求国が服従しないので、軍事力を行使する。すなわち、「初め、稜(陳稜)、南方諸国人を将(ひき)いて従軍せしむ。[山昆]崘人の頗る其の語を解する有り。人を遣わして之を慰諭せしむ。流求従わず、官軍に拒逆す。稜、撃ちて之を走らしめ、進みて其の都に至る。頻りに戦いて皆敗る。其の宮室を焚き、其の男女数千人を虜にし、軍実を載せて、而して還る。爾(こ)れ自(よ)り遂に絶つ」(流求国伝)という。
[山昆]崘人の[山昆]は、JIS第4水準、ユニコード5D10
ところで、何蛮らが流求についての知識をえたのは、[山昆]崘人からではあるまいか。陳稜の流求征討軍には、流求語をよく解する[山昆]崘人が従軍している。[山昆]崘は、『旧唐書』林邑国伝に、「自林邑以南、皆巻髪黒身、通号為[山昆]崘」(巻一九七・列伝第一四七・南蛮・西南蛮)とあるように、現在のベトナム南部・カンボジア・タイ・ビルマ・マレー半島などの諸国の汎称であるという。[山昆]崘人については、『日本書紀』皇極天皇元(六四二)年二月丁亥朔戊子条に、百済の弔使の[イ兼]人(ともびと)等が「百済の使者、[山昆]崘の使を海裏に擲(なげい)れたり」といったという記事がある。また、『唐大和上東征伝』(淡海三船、宝亀一〇年・七七九)によると、天宝一二(七五三)年鑑真和尚に従って渡日してきた弟子達のなかに[山昆]崘人軍法力がいる。[山昆]崘人は、古代の大航海民族であったようである。一方、流求人も、陳稜らの船艦をみて「以て商旅となし、往々軍中に詣で貿易す」(陳稜伝)とあるように、交易には慣れていたのである。
[イ兼]人(ともびと)の[イ兼]は、JIS第3水準、ユニコード5094
流求国は、隋の不法な侵略にたいして国交を絶ち、唐とも公式の国交を開いていない。しかし、流求と唐との間に交渉はあった。『送鄭尚書序』(唐・韓[兪/心]、大暦三年〜長慶四年・七六八〜八二四、明『朱文公校昌黎先生集』巻二一所収)には、流求など海外雑国が広州に通商に来る、『嶺南節度使饗軍堂記』(唐・柳宗元、大暦八年〜元和一四年・七七三〜八一九、『柳河東集』巻第二六所収)には、流求(如)貿易は広州押蕃船使の統を受けていた、とある。
唐の開元通宝(高祖六二一年初鋳)は、沖縄の兼久原貝塚・熱田貝塚・連道原貝塚・野口貝塚群・具志川グスク・勝連(かつれん)城跡・普天間宮洞穴などから数多く出土しているし、乾元通宝(肅宗七五八年初鋳)も今帰仁(なきじん)城跡から出土している。開元通宝は、久米島の北原貝塚で一三枚、遣唐使船の寄港が考えられない西表島・石垣島といった八重山地域でも発見されている。(63) これらの銭貨は、唐と流求との交渉を物語っている。もちろん、日本人・新羅人を経由してもち込まれたものもあろう。
『嶺表録異』(『説庫』一所収)は、唐の昭宗(八八八〜九〇三年)のときに広州司馬となった劉恂(りゅうじゅん)が、広州を主とする嶺南地方の物産・風土を記録した書であるが、流求も採録されている。陸州の刺史であった周遇が、[門/虫]に帰国するとき、海路悪風に遭い五昼夜漂流し六国を経由した漂流譚のなかに、「また流国を経る。其の国人は幺麼(ようま 短小)、一ガイ*(ひとしく)皆麻布を服し、礼有り。競いて将に食物をもって釘鉄かと易(か)えんことを求む。新羅の客また半ば其の語を訳す。客を遣りて速く過さしむ。『此の国は華人が瓢泛して至るに遇えば、[宀/火]禍あるを慮ると言う』と」とある。この漂流譚は、朱寛の来訪につづいて陳稜の流求攻撃があったことを、流求人がいまだに憶えていたことを記録しているようにみえる。そして、新羅人がなかば流求語を知っている事実は、少くとも新羅から流求に、しばしば交易にくる人々があったことを示している。
『朝野僉載(せんさい)』は、唐の張[族/烏](武后朝〜玄宗朝前期)が、主として武后一代(六八四〜七〇四)の朝野の見聞を記したものであるが、一旦散佚し『太平広記』(宋・李[日方]等撰、太平興国三年・九七八)などに収録された逸文が輯録されている。そのなかに、『隋書』流求国伝にはない、流求国の産物と捕虜についての記事がある。ただし、「煬帝、朱寛をして留仇(即ち後の流乢*なり)国を征伐(うた)しむ。男女の口千余人を獲て還る」と陳稜が朱寛となったり、男女数千人が千余人となっている点は、『隋書』とは異なる。
しかし、流求国は鉄を産出しないので、捕虜の流求人が自分の首に枷せられた鉄の鉗樔*を解かれたとき、あたかも貴金をとり上げられるかのように頭を叩いて惜しんだなど、興味深い記事が残されている(『太平広記』巻四八二所引)。
このように、唐代には、唐と流求との間には交易・遭遇があり、隋の流求侵攻の記憶をいまだ両国とも忘却していなかったのである。唐代に編纂された『隋書』『北史』『通典』の流求についての記事も、両国の間に交渉があった時代に書かれている。『通典』の流求国は「[門/虫]川之東」にあり、倭国は「大較在会稽[門/虫]川之東」、という割注も、『隋書』の記事を新しい知識によって再検討し、その方位をさらに明確にするために、加えられているのである。
[宀/火]は、宀の下に火。JIS第4水準、ユニコード707E
一ガイ*(ひとしく)のガイ*は、JIS第3水準、ユニコード69E9
張[族/烏]の[族/烏]は、族の下に烏。JIS第4水準、ユニコード9DDF
乢*の山の代わりに虫。JIS第3水準、ユニコード866C
樔*は、木の代わりに鉄。JIS第4水準、ユニコード93C1
[門/虫]は、門の中に虫。JIS第3水準、ユニコード95A9
『隋書』の流求に関する記事の基本資料は、朱寛・何蛮・陳稜・張鎮州らの公式報告と流求人捕虜の尋問記録であろう。陳稜・張鎮州は、俘虜数万を得(食貨志)、男女数千人を虜にして帰還し(流求国伝・陳稜伝)、大業六(六一〇)年二月乙巳煬帝に俘万七千口を献じ、百官に頒賜された(煬帝紀上)。「俘万七千口」は、陳稜・張鎮州の煬帝あての公式文書の数字であろう。『三国志』(西晋・陳寿、三世紀末)には、賊軍を撃破した場合の公式文書では、(斬首・捕虜の数について)一を十と(十倍に)計算する習慣であったとある(巻一一・国淵伝)。隋代でも同様であったとしても、「千七百口」もの流求人捕虜が、百官に頒賜されている。『隋書』の帝紀・列伝が完成した貞観一〇(六三六)年には、捕虜の多くはまだ生存していたと思われる。しかも、陳稜・張鎮州の遠征軍は、一万余人であったというのであるから、その将兵をはじめ艦船の船師たちも、多数現存していたことも確実であろう。
かりに、「大業中南荒朝貢者十余国、其事迹多煙滅而無聞、今所存録、四国而巳」(『隋書』巻八二・列伝第四七・南蛮伝序文)とあるのと同様に、流求国についての公式記録が煙滅していたとしても、流求遠征軍の将兵・船師に再報告させたり、捕虜を再尋問して、記録を再現できたのである。
流求=沖縄説の論者の多くは、『隋書』流求国伝の記事には、誤伝や誇張がある、伝聞によるものがあり信用できない、あるいは台湾の風俗・動植物相が混入しているという。しかし、『隋書』流求国伝の記事は、そのように疑っておよび腰になったり棄て去るまえに、原則として事実であるという観点から、真剣に検討されるべき問題ではないだろうか。
隋に連れ去られた流求国の捕虜達のその後の運命は、どうなったのか?それに答える手がかりはある。
『[門/虫]書』(明・何喬遠編、崇禎四年・一六三一)の福州府福清県福盧山の条には、「三十里為化南化北二里、隋時掠琉球五千戸居此」(巻六・方域志)とある。そして、福清県の南西、福建省仙遊県の砂糖工場の裏にある石畳の小路の石に、お椀大の図象文字が刻まれている(その石は、近くの山の上から運んできたものであるという)。その図象文字は、明治時代まで与那国島で用いられていた「与那国文字(カイダー字)」といわれるものと一致するという。(69) 捕虜やその子孫が、故郷を偲んで刻んだものであろうか。それとも、いつのころか交易にいった与那国島民が刻んだものであろうか。
ところで、沖縄の歴史は、古墳時代から平安時代までの期間は、あたかも歴史がストップしていたかのようにまったくの空白になっているという。(70) この期間に相当する沖縄考古学の時代区分は、貝塚時代後期のフェンサ下層式土器あるいは類須恵器の時代として、ひとまとめにくくられている。その原因は、考古学的な調査研究の遅れだけではなく、『隋書』の流求国が現在の沖縄であることに確信がなく、その記事が当時の沖縄の実態を正確に記述しているとは受けとられていないことにある。
遺跡からの出土物については、放射性炭素年代法による年代測定を実施し、『隋書』流求国伝が七世紀初頭の沖縄を記録している基本文献であるという認識のもとに、出土物を検討すれば、稲作農耕・鉄器文化・グスクの発生・開始時期などの問題も、ヨリ精緻に論じることができるようになり、歴史の空白も埋まっていくのではないだろうか。
沖縄には、縄文時代早期から九州系の土器文化が、つぎつぎと南下し押寄せてきている。(71) 縄文晩期には、沖縄に佐賀県腰岳産の黒曜石がもたらされ (63)、北九州では貝製腕輪が使用されるようになる。(72)(73) そして、最近では、沖縄の貝塚時代後期初頭の遺跡からは、移入された弥生式土器の出土が相次ぎ、同時に鉄斧や砥石・箱式石棺墓といった弥生文化を特徴づける文物が確認されるなど、弥生文化の定着を証す資料は、確実に増えつづけているという。弥生時代の北九州には、沖縄産のゴホウラ製貝輪 (75)(76)(77) が大量に送り込まれているが、鉄と交換したのではあるまいか。
ところが、沖縄には古墳文化は存在しないという。しかし、北九州の弥生文化の構成要素のなかでも甕棺葬の風習は、沖縄には渡ってきていないのである。古墳がないからといって、古墳時代以降、九州の文化が突然沖縄に入ってこなくなったとは、考えられない。
隋に来朝していたイ妥国の使者は、朱寛が取って還った流求国の布甲をみせられて、「此れ、夷邪久国人の用うる所なり」と、尾久島で使用していることを認めている。イ妥国(=倭国)と流求国は、地理的にも近く、風俗の面においても共通のものを持っているのである。それだけではなく、倭国と流求国とは、貝の道によって結ばれていたように、政治的にも、ずっと密接な関係を保っていたのではないだろうか。
琉球国最後の正史『球陽』(蔡温等纂、延享二年・一七四五)は、流求の国君のはじめは天孫氏であるという。古田武彦のいう倭国=九州王朝の祖先も「天国(78)」の出身、同じ海人族の天孫氏である。天孫氏の裔孫による流求国の治政は、「交譲相伝ふこと、凡そ二十五紀、乙丑に起て丙午に尽る。一万七千八百有二年を歴る」という。丙午は、権臣利勇が国君を殺した一一八六年(南宋・淳煕一三年)にあたる。天孫氏の治政が、乙丑に始まり丙午に終るという干支は、『中山世鑑』にはじめてあらわれる。しかし、その原記録は、結縄刻木に残されていたのではないか?
沖縄の結縄刻木(バラサン、スーチューマ・カイダー字)と、『隋書』イ妥国伝に「文字無し、唯木を刻み縄を結ぶのみ。仏法を敬す。百済に於て仏経を求得し、始めて文字あり」という、倭国の結縄刻木との関係は、別に論じることとしたい。
この論文を書くにあたっては、横山妙子氏の協力により文献を収集することができた。記して感謝します。
〈注〉
(1) 秋山謙蔵「流求即台湾説成立の過程」(『歴史地理』五八 ー 六、一九三一)。
(2) 箭内亙『東洋読史地図』、一九一二(改訂増補版・一九三一)。
(3) 藤田豊八『島夷誌略校注』、一九一五。
(4) 藤田豊八「琉求人南洋通商の最古の記録」(『史学雑誌』二八 ー 八、一九一七)、後に『東西交渉史の研究』南海篇(一九七四)に収録。
(5) 鈴村譲「琉球弁」(『台湾海峡』、一九一六)。
(6) 市村讚*次郎「唐以前の福建及び台湾に就いて」(『東洋学報』八 ー 一、一九一八)、後に『支那史研究』(一九四三)に収録。
市村讚*次郎の讚*は、言偏の代わり王編。JIS第三水準、ユニコード74DA
(7) 和田清「琉球台湾の名称に就いて」(『東洋学報』一四 ー 四、一九二四)。
(8) 和田清「再び隋書の流求国について」(『歴史地理』五七 ー 三、一九三一)。
(9) 伊能嘉矩「隋書に見ゆる琉球の人称名及土地名と台湾の蕃言との近似」(『東京人類学会雑誌』二四六、一九〇六)。
(10)伊能嘉矩「台湾と琉球」(『東京人類学会雑誌』二六五、一九○八)。
(11)伊能嘉矩『台湾文化志』上、一九二八(復刻版・一九六五)。
(12)幣原坦「琉球の支那に通ぜし端緒」(『史学雑誌』六 ー 九、一八九五)。ただし、次の(13)と共に、流求=沖縄説である。
(13)幣原坦『南島沿革史論』、一八九九。
(14)幣原坦「台湾の瑯僑*族」(『民族』四1一、一九二八)。
瑯僑*族の僑*は、人編の代わりに山編。JIS第三水準、ユニコード5DAO
(15)幣原坦「琉球台湾混同論争の批判」(『南方土俗』一 ー 三、一九三一)。
(16)曽我部静雄「所謂隋代流求に就いての異聞二つ」(『歴史と地理』二九 ー 一、一九三二)。
(17)曽我部静雄「再び隋代の流求について」(『歴史と地理」二九 ー 六、一九三二)。
(18)白島庫吉「『隋書』の流求国の言語に就いて」(『民族学研究』一 ー 四、一九三五)、後に『白島庫吉全集』九(一九七一)に収録。
(19)甲野勇「隋書『流求国伝』の古民族学考究(予報)』(『民族学研究』三 ー 四、一九三七)。
(20)加藤三吾『琉球の研究』、一九〇七(改訂版・一九七五)。
(21)東恩納寛惇『大日本地名辞書』続編・第二琉球、一九〇九(増補版・第八巻、一九七〇)、後に『東恩納寛惇全集』六(一九七九)に収録。
(22)東恩納寛惇『南島風土記』、一九五〇、後に『東恩納寛惇全集』七(一九八○)に収録。
(23)東恩納寛惇「隋書の流求は果して沖縄なりや」(『東恩納寛惇全集』一、一九七八)、初出・『沖縄タイムス』一九二六。
(24)東恩納寛惇「伊波君の修正説を疑ふー隋書の流求に就きー」(『東恩納寛惇全集』一、一九七八)、初出・『沖縄タイムス』一九二七。
(25)種村保三郎『台湾小史』、一九四五。
(26)宮良當壮「琉球民族とその言語」(『民族学研究』一八 ー 四、一九五四)後に『宮良當壮全集』一七(一九八二)収録。
(27)桑田六郎「上代の台湾」(『民族学研究』一八 ー 一・二、一九五四)。
(28)国分直一「会稽海外の国ー台湾と琉求をめぐって」(『古代文化』二三 ー 九・一○、一九七一)、後に『南島先史時代の研究』(一九七二)に収録。
(29)金関丈夫「『諸蕃志』の談馬顔国」(『南方文化誌』、一九七七)。初出・日本人類学会、日本民族学協会第七回連合大会、一九五三。
(30)李家正文「流求と称した台湾」(『東アジア史の謎』、一九八五)。
(31)中馬庚「台湾と琉球との混同に付て」(『史学雑誌』八一 ー 一一、一八九七)。
(32)隅本繁吉・中馬庚「台湾琉球との混同に付て(承前)」(『史学雑誌』八 ー 一二、一八九七)。
(33)秋山謙蔵「隋書流求国伝の再吟味」(『歴史地理』五四 ー 二、一九二九)。
(34)秋山謙蔵「流求即台湾説再批判」(『歴史地理』五九 ー 一、一九三二)、後に(1)・(33)と共に『日支交渉史話』(一九三五)に収録。
(35)秋山謙三「唐と琉球」(『ドルメン』二 ー 七、一九三三)。
(36)喜田貞吉「隋書の流求伝に就いて」(『歴史地理』五四 ー 三、一九二九)。
(37)喜田貞吉「隋書流求の民族的一考察」(『歴史地理』五九 ー 三、一九三二)。
(38)M・C・アグノエル「隋書の流求を台湾に比定せんとする ーー試案に対する批判」(『歴史地理』五八 ー 五、一九三一)。
(39)藤田元春『日支交通の研究』中近世編、一九三八。
(40)梁嘉彬『琉球及東南諸海島与中国』、一九六五。
(41)梁嘉彬「宋諸蕃志流求国[田比]舎耶国考証」(『大陸雑誌』四四 ー 一、一九七二)。
(42)梁嘉彬「隋書流求国伝逐句考証」(『大陸雑誌』四五 ー 六、一九七二)。
(43)松本雅明「南島の世界」(『古代の日本』三、一九七〇)。
(44)松本雅明『沖縄の歴史と文化』、一九七一。
(45)松本雅明「南島における文化の交流」(『九州文化論集』I、一九七三)。
(46)松本雅明「伊波普猷氏と『隋書』流求伝」(『伊波普猷全集』二・月報、一九七四)、後に(43)〜(45)と共に『松本雅明著作集』二(一九八六)に収録。
(47)比嘉春潮『沖縄文化史』、一九六三、後に『比嘉春潮全集』一(一九七一)に収録。
(48)川越泰博「『隋書』流求国伝の問題によせて」(『中国典籍研究』、一九七八)。
(49)本位田菊士「古代環シナ海交通と南島 ーー『隋書』の流求と陳稜の征討をめぐって」(『東アジアの古代文化』二九、一九八一)。
(50)大林太良・谷川健一・森浩一編『シンポジウム 沖縄の古代文化』(一九八三)における森浩一の発言(九五〜九八頁)。
(51)古田武彦『法隆寺の中の九州王朝』古代は輝いていたIII〈朝日文庫〉、一九八八。
(52)村井章介「古琉球と列島地域社会」(『新琉球史』古琉球編、一九九一)。
(53)伊波普猷「『隋書』に現れたる琉球」(『沖縄教育』一五七・一五八、一九二六)。
(54)伊波普猷「『隋書』の流求に就いての疑問」(『東洋学報』一六 ー 二、一九二七)、後に(53)と共に『伊波普猷全集』二(一九七四)に収録。
(55)鈴木靖民「南島人の来朝をめぐる基礎的考察」(『東アジアと日本』歴史編、一九八七)。
(56)真栄平房昭「琉球の形成と東アジア」(『新版古代の日本』三、一九九一)。
(57)田中健夫「東アジアの文献に誌された『琉球』」(『南の王国琉球』、一九九二)。
(58)田中健夫・石井正敏『古代日中関係編年史料稿」(『遣唐使研究と史料』、一九八七)。
(59)高良倉吉「王国の成立」(『図説 琉球王国』、一九九三)。
(60)古田武彦「日本書紀の史料批判」(『文芸研究』九五、一九八○)、後に『多元的古代の成立』上(一九八三)に収録。
(61)『日本書紀』巻二七・天智天皇、(1)三年夏五月戌申朔甲子条・(2)四年九月庚午朔壬辰条・(3) 六年一一月丁巳朔乙丑条・(4) 一〇年正月辛亥条・(5) 一〇年一一月甲午朔癸卯条。
(62)野口鉄郎『中国と琉球』、一九七七。中国正史の全流求国伝の訳注書である。
(63)宮城栄昌・高宮広衛『沖縄歴史地図』考古編、一九八三。
(64)原田禹雄訳注『完訳中山伝信録』、一九八二。
(65)石島英「季節風・海流と航海」(『海洋文化論』環中国海の民俗と文化 I、一九九三)。
(66)藤善真澄訳注『誌蕃志』関西大学東西学術研究所訳注シリーズ5、一九九一。
(67)馬淵東一は、「明らかに台湾について述べていると考えられる最古の文献は、南宋時代の樓鑰(一一三七〜一二一三)の『攻魏集』である。これには、澎湖島に関する記述が見られる」という(宮本延人・瀬川孝吉・馬淵東一『台湾の民族と文化』、一九八七)。『攻魏集』行状条(巻八八)に、汪大猷(南宋・孝宗の頃・一一六二〜一一八九)が泉州の長官となった乾道七(一一七一)年、[田比]舎邪という島夷が平湖(彭胡)を襲ったとある。『宋史』汪大猷伝(巻四〇〇・列伝第一五九)にも、[田比]舎邪が泉州の海浜の居民を掠めたり、境を犯すとある。
(68)石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』中国正史日本伝(1)〈岩波文庫〉、一九八五。
(69)劉恵*孫「中国・琉球往来史の探究」(『琉球 ーー中国交流史をさぐる」、一九八八)。
劉恵*孫の恵*は、草冠に恵。JIS第三水準、ユニコード8559
(70)當眞嗣一「考古遺跡は語る」(『新琉球史』古琉球編、一九九一)。
(71)新東晃一「海を渡った縄文土器」(『図説 発掘が語る日本史』六、一九八六)。
(72)渡辺誠「縄文時代における貝製腕輪」(『古代文化」二一 ー 一、一九六九)。
(73)前原市教育委員会編『伊都 ーー古代の糸島』、一九九二。
(74)岸本義彦「沖縄出土の弥生土器瞥見〔I〕」(『南島考古』八、一九八三)。
(75)三島格『貝をめぐる考古学 ーー南島考古学の一視点』、一九七七。
(76)木下尚子「弥生時代における南海産貝製腕輪の生成と展開」(森貞次郎博士古稀記念『古文化論集』上、一九八二)。
(77)柏原精一「貝∴南海の道が証明された」(『図説邪馬台国物産帳』、一九九三)。
(78)古田武彦『盗まれた神話 ーー記・紀の秘密』〈角川文庫〉、一九七九。