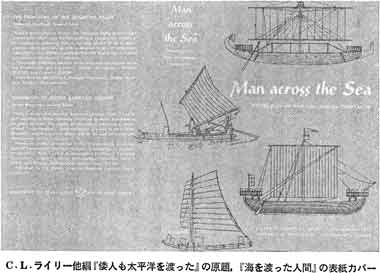
『邪馬一国への道標』(目次) へ
第一章 縄文の謎(なぞ)の扉を開く
一 縄文人が周王朝に貢献した ーー『論衡ろんこう』をめぐって
おわりに 解説にかえて《対談》夢は地球をかけめぐる ーー小松左京さんと語る
『邪馬一国への道標』(角川文庫)
講談社版 角川文庫版
古田武彦
わたしが第一作『「邪馬台国」はなかった』を世に問うてから、はや六年余。その後も、孤立の道を歩んできました。古代史の諸大家の説に訣別(けつべつ)し、学界の一隅に身を置くことをせず、ただ自分自身のために、ひとつひとつの真実を求めつづけてきたのです。
自分という、ささやかた人間の目で“なるほど、そうだ”とうなずけるものだけ、珠玉として掌(たなごころ)の中ににぎりしめ、これを喜びとし、他はかえりみませんでした。このようなわたしの姿を偏狭とし、冷笑をかたむけ、てんぜんと無視してきた学界や文筆界の大家たち。しかし、それらはすべて予期したこと。わたしには今さら何の感慨(かんがい)もさそいませんでした。
けれども、そのようなわたしに向かって、淋しくはないか、と問われれば、すぐさま「否!」と答えをかえすことができます。なぜなら、わたしのまわりには、若い友人やささやかな家族たちがいます。彼らはわたしの新しい思いつきを聞いて、あるいはうなずき、あるいは容赦なくかぶりをふってくれるのです。ですから、その人々はわたしにとって“無上の師”なのです。女や子供や青年たち、また年老いた賢明な人たち。 ーーわたしの学問の、尽きざる源泉に、わたしはいつも囲まれているのですから。
その上、第一作を世に出してから、予期しなかった経験に遭遇しました。多くの読者たちからの、ひっきりなしの手紙。それには真率(しんそつ)な反応の渦(うず)があふれ、あるいは孤立のわたしを慰め、あるいは静かに激励し、いつもわたしを支えてくれる、力強い大樹となっています。
さらに一昨年来、東京や大阪に自然発生的に楽しい会が生れました。読者の会です。それらの会に招かれて、わたしの語ったこと、またこの本を書いてゆく中で ーーいつものことですがーー 偶然見つけた、新しい課題。それらがここに盛られています。よく見ていただければ、それらには無数の新たな探究への光源がふくまれていることをお目にとめていただけることと思います。わたしが発見した新倭国(わこく)史料の重要な断片、それらの数々をこの本の中ではじめて明確に報告できたことを喜びとします。
ですが、この本の最大のねらい、それは次の一点です。かみしもを全くぬぎすてて読者のひとりひとりの方とじっくりお話してみよう。そういった感じで一行一行書きこんでいったことです。“こんな話、あるか”と憤慨していただいても結構。ここからさらに新しいアイデアをふくらまして下さっても、なお結構。要するにこれがわたしの、いつわらぬ今の声なのです。竹の林の朝夕の風の中からこぼれ落ち、ひろいあげたひとつ、ひとつ。このわたしのつぶやきがどなたかの胸の底深くにとどくなら、それほどの幸せはありません。
最後に、小松左京さんとの対談をこの本にのせることができたのは、望外の幸。久しぶり、談論風発の喜びを味わいました。
なお、この文庫本を出すについて、市川端さん(講談社)と松田達さん(角川書店)をはじめ、お世話になった関係の方々に深い感謝をささげたいと思います。
(なお、この本を出すについて、ご厄介をかけた講談社の市川端さんと松本信子さんに感謝いたします。)
昭和五十七年五月下旬 (角川文庫版)
昭和五十三年四月五日 (講談社版)
古田武彦
古田武彦
昭和五十二年(一九七七年)の暮れから新発見がつづいています。古代史の文献方面と言わず、考古学方面と言わず、目まぐるしく新局面があらわれ、それこそ“応接にいとまがない”感じです。久しく遠ざかっていた私自身の研究テーマ・親鸞(しんらん)ついてさえ、続々“新史料”の再発見があり、「何でこんなことが、今までに発見されなかったんだろう」と思う昨今なのです。
この六〜七月など、寝ても覚めても、あまり“新発見や再発見”がつづくので、私の単純な頭の機械が焼け切れそうで、“頭よ止まれ!”と思わず叫びたくなったほどでした。どうも、“私”が考えているのではない。ただ“考え”が私の頭を借り切っているだけなのではないか、そんな気ちがいじみた想念さえ浮かびました。
そこで、今のうちにそれを書きとめておこう、と思い立ったのです。それもこれまでのような文体(スタイル)じゃない。ザックバランな語り口で・・・ 。
今までの私の古代史の本は、言ってみれば二正面作戦でした(『「邪馬台国」はなかった』、『失われた九州王朝』、『盗まれた神話』、『邪馬壹国の論理』)。
片一方に専門家たち、学者、大家先生方の“批判の目”があります。今までの日本の古代史の“間尺(まじゃく)にあわない”とてつもない結論を次々と展開するのですから、二重、三重に論証の装備をしなれば、嘲笑(わらわ)れてしまいます。「これでもか、これでもか」と、論証に論証を重ねて全身“針ねずみ”のように身がまえたのです。ところが、他の一方には読者がいます。もってまわった論文調の物の言い方でなく、率直に・ストレートに書きすすめてゆかなければ、とても“読めた”ものではありません。
もっとも、この“率直な書き口”は、わたし自身にとってすごく有益でした。もってまわった論文調なら“ごまかせる”ところが、ごまかせないのです。「・・・だ」と書いたとたん「なぜそうなのだ」という反問が、自分の中から生れます。それがわたしを、しばしば新局面へと導いたのです。それはともあれ、こんな二正面作戦のため、少々本が“重苦しく”なったことはやむをえません。あのような内容の本の場合、それは、とりうる“唯一の選択“だったかもしれませんがーー 。
今回は、それとはちがったやり方をしたい、そう思っています。もっとストレートに“語り”たいのです。
たとえば、洛西(らくせい)の竹藪(たけやぶ)の片ほとりの、わたしの住まいに、わざわざ訪れて下さった熱心た読者の方があった、とします。たった一人で、朝も夕も探究にとりくんでいるわたしは、“人恋しい”思いになっていて、最近の自分が到達した発見を、次々語り出すかもしれません。何も、もってまわった前おきやかたくるしい“重装備”なしに、ひとつ、ひとつ、自分が当面し、目撃してきた課題を“投げ出してゆく”でしょう。
そんな風に、この本でも“語り”たいのです。ですから、わたしの書斎(というほどのものではありませんが)の中で、本に埋もれて、たった二人くらいしか坐れない場所で、わたしと向いあっている、そんな感じで“聞いて”下さったら、幸いです。
五十一年はわたしにとって“変った”年でした。来る夜も来る朝も、昼中も、ズーッと机の前に坐って、大きな英語の辞書と首っ引き。そんな毎日でした。
『Man across the Sea』というアメリカの考古学の本です。五十二年の初夏、『倭人(わじん)も太平洋を渡った』という訳書名で、東京の創世記から刊行されましたから、ご覧いただいた方もあるか、と思います。この作業は、存外、わたしにとって楽しい仕事でした。英語を習いはじめの中学生よろしく、“一字一字全部辞書で引く覚悟”ではじめたのですが、ひとつひとつの論文の“言葉のひだ”を読みとれた、と思うとき、何とも言えず愉快でした。
江戸末期、杉田玄白(すぎたげんぱく)の書いた、あの『蘭学事始らんがくことはじめ』に出てくる、有名な挿話(エピソード)がありますね。「フルヘツヘソド」というのが何を意味する言葉か。みんた手さぐりで四苦八苦する話です。あれ、さながら・・・・・。たとえば一例。“pre-Anyan”たどという単語が出てきましたが、辞書にありません。わたしの手持ちの辞書類や百科事典などをさんざん渉猟しても、全く見当もつきません。あげくの果て、ギリシア語やラテン語の辞書まで引っばり出す仕末でしたが、やはり駄目。京大の図書館などであちら(米、英)の大百科辞典など種々探しあぐねてもわからず、ある朝、ふとしたきっかけで“Anyan”は「安陽あんよう」という中国の地名だ、と気づいたときのうれしさ。飛びあがりました。
安陽は、有名な殷墟(いんきょ)が出土した地域です。ですから、そこから出土しながら、いわゆる殷の時代をさらにさかのぼる地層から出た遺物。それを呼んだ言葉だったのです。そこで、「先殷期」と訳しました。わたしたちは、その時期が中国の古典で「夏か」と呼ばれていたことを知っています。そう、あの聖天子・禹(う)が創建した、と伝えられる夏王朝。あの時代です。
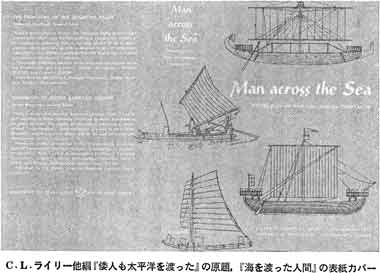
話が横道に入りましたが、本筋にもどりましょう。
この本を訳してゆく中で、 ーーわたしがハッと思った個所。それは次の言葉です。
「世界の島、海岸、そして河岸の多くの住民にとって、水は彼等を“隔(へだ)てる”ものではなかった。水はむしろ彼等を“結合”したのだ」
(『倭人も太平洋を渡った』一四九頁)。
これは一九六五年、C・R・エドワーズという学者がのべた言葉です。
「もし何一つない海をへだてて二つの陸領域が相対しているなちば、その分布は、真の意味では正に連続的なのである」(同右、一五五頁)。これは、この本の中でもっとも精力的な力作を“ものしている”スティーブン・C・ジェットの言葉です。この二人の言いたいことは一つ。“海は、文明の伝播(でんば)にとって、「障害」ではない。見事な、天然の通路なのだ”と。同じ立場から、すばらしいスケールの“思想”をしめしたのは、ソビエトの学者アルティウノフです。彼は一九六六年、一つの“造語”を発表しました ーー「アメロトララシア」(Amerautralasia)。
ご存じの方もあると思いますが、「アフロユーラシア」という造語があります。アフリカとユーラシア大陸(ヨーロッパ、近東)とを“打って一丸として”、一語としたものです。何のために。地中海を“アフロユーラシアの内海”だ、と考えるため、です。アルティウノフは、このアイデアを拡大しました。アメリカ両大陸(America)と大洋州(Australia)とアジア(Asia)とを、“打って一丸とした”のです。そして言ったのです。「太平洋は、アメロトララシアの内海だ」と(右書、一五五頁)。
言われてみれば、その通り。何の変哲もない話ですが、何とスケールの大きな“造語”でしょう、“思想”でしょう。その太平洋の一隅の島々に住む、わたしたち日本人の学者の中から、このアイデアが生れたかったのが不思議です。何か“お恥かしい”感じさえします。
わたしは、五十二年のはじめ、NHKの「スタジオ102」で話したとき、このアルティウノフの説を紹介しました。ただし、「アメロトララシア」では、日本人には一口に言いにくい。言ってみても、憶(おぼ)えにくい。そこで、日本人向きに“造語し直して”みましたー「アジメリア」と。そう、やはりアジアとアメリカとオーストラリアを“とりまとめた”ものです。これなら、日本人にも言いやすい、と思うのですがーー。
そのとき、わたしは考えました。“中国大陸と朝鮮半島と日本列島(九州と沖縄)に囲まれた海” ーーこれも「内海」ではないか、と。そして東アジアの歴史を考える上で、この「内海」のもつ意義は絶大なのではないか、と。
朝鮮半島の歴史も、日本列島の歴史も、この「内海」の存在を抜きにして語れないのではないでしょうか。はるか悠遠(ゆうえん)な古代も ーー、そして現代も。ところが、この「内海」には、包括的(トータル)な名前がありません。北の方が渤海(ぼっかい)、真ん中が黄海、南の方が東シナ海。しかし、全体の名前がないのです。そこで“造る”ことにしました。 ーー「中国海」です。お隣りの日本海や朝鮮海峡に比べてみても、これしかない。わたしにはそう思えたのです。
中国大陸の東岸域が、この三つの海にズーッと臨んでいるのですから、まず妥当な“命名”ではないか。自画自讃めいて恐縮なのですが、これがわたしの気持でした。とすると、中国、朝鮮半島、日本列島の三つは、“中国海を内海とする”文明圏だ。こういうことになります。これは東アジアの歴史を考える上で“地政的に(政治現象と地理的条件との関係、といった目から)”根本的な視点ではないでしょうか。
先達があります。「環東シナ海文明圏」という言葉です。古代史家・国分直一(こくぶなおいち)さんだったでしょうか。「環太平洋圏」という言葉にならって作られたものと思います。中国の江南と朝鮮半島南部、九州、沖縄列島が東シナ海を媒介として結ばれていた、 ーーこういう“思想”でしょう。その通りです。たとえば有名な「稲の道」を考える上でも、これは欠かせぬ見地でしょう。
しかし、この“思想”は、もっと大胆に拡大する必要があります。 ーー「環中国海圏」です。これが東アジアの歴史の中で、いつも“活気ある一世界”として存在しつづけていたのです。
さて、わたしは翻訳という、苦しいけれど、なぜか心楽しい作業の中でいつも一つのフラストレーション(欲求不満)をもちつづけていました。“自分も、日本の古代史の探究に再びとりくみたい”。そういう気持がうずうずして、おさえきれませんでした。
一つには、目の前の「原文」の中で、アメリカの考古学者たちが自由に大胆闊達(かったつ)に自分自分のイメージをふくらませた刺戟(しげき)的な論議をくりひろげていたからでしょう。自分も、その論議の中に入って一緒に論争したい。“翻訳者”としては不謹慎な願いかもしれませんが、そういう“自分の中の声”と闘いながら、作業をつづけていたのです。そんな状況でしたから、昨年の秋の末、翻訳が終ると同時に、日本の古代史の森の中に、待ちかねたように飛びこんでいきました。ちょうど、真夏の太陽の中の旅人がオアシスをひそめた森のたたずまいを見つけたときのように。
わたしは京大の人文科学研究所の図書館に行き、『論衡ろんこう』という本を探し求めました。中国の古典かどでは東洋で、否、全世界で屈指の所蔵量とその質を誇っている、ここは、わたしにとってまことに有難い“宝庫”です。目録をくると、すぐ何種類かの『論衡』が出てきました。それを借り出して閲覧室で読み進むうち、わたしはハッと胸を突かれました。他人(ひと)が見たら、きっと“顔色を変えて”いたにちがいありません。
ーーやがて夕暮れ。閉館時間にたって晩秋の京都の冷え冷えした空気の中に立ったとき、わたしは興奮が全身を“熱く”ひたしているのを感じていました。
『邪馬壹国の論理』 へ